仕事でミスが続いたり、大切な予定をうっかり忘れてしまったり、働き盛りの世代でこうした変化が起こると、「もしかして若年性認知症では?」と不安になるかもしれません。ご本人はもちろん、一緒に生活するご家族も戸惑い、どう対処すればよいのか悩まれることでしょう。この記事では、若年性認知症の初期症状や性格・行動の変化、早期発見のためにできること、診断後に利用できる支援制度を解説します。
若年性認知症とは

認知症は高齢者に発症すると思っている方もいると思います。本章では若年性認知症とその発症しやすい年齢などについて解説します。
若年性認知症の概要
若年性認知症とは、65歳未満の若い年齢で発症する認知症の総称です。医学的には高齢者の認知症と症状自体に大きな違いはなく、もの忘れや判断力の低下などがあります。しかし、この世代で発症すると仕事や家庭の状況に大きく影響します。実際、若年性認知症と診断された方の全国推計数は約3万5,700人と報告されており、なかには退職などを余儀なくされる方がいらっしゃいます。
若年性認知症を発症しやすい年齢
若年性認知症は若い世代(働き盛り世代)で発症します。平均発症年齢は50歳前後ですが、40代で発症する方も珍しくありません。ある調査では、最初に症状に気付いた年齢の平均は54.4歳で、そのうち約30%は50歳未満だったと報告されています。つまり、多くは40〜50代で発症しますが、なかには30代という若さで発症するケースもあります。ただし、10代や20代で発症するのはごくまれな例です。このように発症年齢に幅はありますが、「まだ若いから認知症になるはずがない」という思い込みは危険です。誰でも発症しうることを念頭に、日頃から症状に気を配ることが大切です。
若年性認知症の初期症状

若年性認知症の初期には、仕事や日常生活上のちょっとした変化やミスとして症状が現れることがあります。典型的にはもの忘れや判断力の低下ですが、症状の現れ方には個人差があり、高齢者の場合と比べて必ずしも物忘れが目立ちにくいこともあります。本章では代表的な初期症状をいくつか見てみましょう。
仕事や日常でのミスが増える
若年性認知症の初期には、これまで問題なくできていた仕事や家事でミスが増えることがあります。例えば職場では、同じ指示を何度も上司に確認したり、同じ商品を重複して発注して在庫を過剰に抱えてしまったりするといったミスが見られる場合があります。家庭でも、いつも作っている料理の手順を間違えたり、何度も鍋を焦がしてしまうことがあります。このように日常的なミスの増加は、認知機能低下のサインの一つです。
段取りや計画を立てにくくなる
物事の段取りや計画を立てることが苦手になるのも初期症状としてよく見られます。複数の作業を同時に進行することが難しくなり、物事を順序立てて進めるのに時間がかかったり、ミスをしやすくなったりします。本人も「段取りよく物事を進められない」と感じることが増えてきます。このように実行機能の低下が起こると、仕事の生産性や家事の効率が下がり始めます。
約束や予定を忘れる頻度が増える
若年性認知症では記憶力の低下も初期から現れることがあります。スケジュール管理がうまくできず約束や予定を忘れてしまう場面が出てきます。例えば、取引先との大事な打ち合わせを失念してしまい、相手から確認の連絡を受けて気付くことがあります。家庭でも、子どもの学校行事の予定を忘れてしまうことがあります。
若年性認知症による性格や行動の変化

認知症が進行し始めると、認知機能の低下に伴って性格や行動面にも変化が現れることがあります。若年性認知症では周囲との人間関係や感情コントロールにも影響が及ぶため、以下のような変化が見られることがあります。
怒りっぽくなる、頑固になる
感情の起伏が激しくなり、些細なことで怒りっぽくなる場合があります。今まで穏やかな性格だった方が急に短気になることもあり、周囲は驚くかもしれません。また、もともと頑固な性格だった方はさらに頑固さが強まって融通が利かなくなることもあります。これは認知症によって脳の前頭葉などがダメージを受け、衝動や感情を抑制する力が低下するためと考えられます。
興味や関心が急に薄れる
意欲や興味の低下も若年性認知症の特徴の一つです。以前は熱心に取り組んでいた趣味や活動に対して、急に興味を示さなくなることがあります。意欲の低下や社会的な引きこもりは、うつ病と勘違いされやすい症状でもあります。趣味や仕事への情熱が急激に失われ、「何をするのもおっくうだ」と感じ始めたら注意が必要です。
うつ病との見分けが難しいケースもある
若年性認知症の初期症状は、一部がうつ病やストレスの症状と似ている場合があります。そのため認知症を疑いにくく、診断まで時間がかかるケースも少なくありません。実際に、仕事のストレスによるうつ病や更年期障害を疑って心療内科を受診しているうちに、実は認知症が進行していたという例もあります。このように若年性認知症はほかの病気と誤認されやすいため、専門医でも確定診断が難しい場合があります。その結果、認知症の症状がかなり進行してからようやく正しく診断されることもあるのです。
本人が気付きにくい理由と周囲の役割

若年性の認知症は加齢に伴う認知症と違い、気付かれにくい点がいくつかあります。本章では本人が若年性認知症に気付きにくい理由と家族や同僚ができることを解説します。
ミスを隠そうとする
若年性認知症のご本人は、症状の初期段階では自分に異変が起きていることを受け入れたくない気持ちが強い傾向にあります。そのため、できるだけミスを隠したり、取り繕ったりしようとすることがあります。認知症の初期にはこうした取り繕い反応が見られることがあり、結果として周囲の方からは変化に気付きにくくなってしまう場合もあります。
疲れや加齢のせいだと思ってしまう
本人が若年性認知症に気付きにくい大きな理由の一つは、自分が認知症になるはずがないという思い込みです。働き盛りの年代では、物忘れやミスが増えてもストレスや加齢の問題に原因を求めてしまいがちです。本人が症状を別の原因だと自己判断してしまうため、認知症とは気付かずに日常を過ごしているケースが少なくありません。
家族や同僚が変化に気付いたときにできること
では、もし家族や職場の同僚など周囲の方がご本人の変化に気付いた場合、どのように対応すればよいでしょうか。まず大切なのは、決して責めたり怒ったりせず、寄り添う姿勢で接することです。ミスを指摘する際も感情的にならず、「何か最近調子が良くないみたいだけど大丈夫?」と体調を気遣う言葉から始めるとよいでしょう。周囲が責め立てると、ご本人はますますミスを隠そうとして心を閉ざしてしまう恐れがあります。代わりに、具体的な事例を穏やかに伝えることが有効です。そのうえで、早めに医師の診察を受けることを促すことが必要です。
若年性認知症の早期発見・受診につなげるためにできること

若年性認知症は疑わしい症状があればできるだけ早く専門医を受診し、適切な対応を始めることが何より重要です。以下に、早期発見・受診につなげるためのポイントをまとめます。
- 「おかしい」と思ったら放置しない
- 受診を促す際の伝え方に配慮する:認知症かもしれないなどと直接的な表現は避け、「最近ストレスが溜まっているのかもね」「念のため病院で検査してみない?」といった別の切り口で提案する方法が有効です
- 受診の際は専門医に相談する
- 早期診断で得られるメリットを知る:診断が早ければご本人も判断力が保たれているうちに今後の人生設計を考える時間が持て、仕事を続けるか退職するか、財産管理や公的支援の利用などについて、本人の意思を反映した計画を立てられるでしょう
以上のように、おかしいと思ったら早めに専門家へという心構えでいることが、若年性認知症に向き合う第一歩となります。周囲の方も協力して、ご本人をスムーズに受診につなげられるよう工夫してみてください。
若年性認知症診断後の生活と支援制度

若年性認知症と診断された後の生活では、本人の症状の進行度や家庭の状況に応じてさまざまなサポート制度を利用していくことになります。ここでは、就労や経済面での支援策、家族ができるサポート体制づくり、そして相談先となる公的機関について説明します。
就労・経済的支援の検討
仕事を続けるかどうかは若年性認知症の当事者にとって大きな問題です。若年性認知症と診断されたからといってすぐに退職せず、上司や人事担当者、産業医と話し合うようにしましょう。業務内容の変更や勤務時間の短縮、部署異動など配慮を得ることができれば、今の職場で働き続けられる可能性があります。場合によっては会社の了承のもと障害者雇用枠に切り替えて勤務を継続する方法もあります。実際、若年性認知症の方に特化した就労支援のガイドラインも作成されており、地域障害者職業センターでは職場復帰支援やジョブコーチによるサポートが受けられる制度も整っています。職場の理解を得ながら、自分のできる範囲で社会参加を続けることは、ご本人の生きがいや収入の維持にもつながります。
家族ができるサポートと体制づくり
若年性認知症と診断された後は、家族の支えと適切な介護体制が欠かせません。若年性認知症の場合、大半は配偶者である夫や妻が主要な介護者となります。この世代は子育てや仕事との両立や、場合によっては自分の親の介護も重なりやすい時期にあります。そのため主介護者の負担が大きくなりがちで、周囲の協力や公的サービスの活用なしには心身がもたなくなってしまう恐れがあります。
公的な介護サービスとしては、40歳以上であれば介護保険を利用することができます。若年性認知症は40〜64歳の介護保険(第2号被保険者)が利用できる特定疾病に含まれているため、要介護認定を受ければデイサービス(通所介護)やホームヘルパー(訪問介護)、ショートステイ(短期入所)など高齢者と同様の介護サービスを受けることができます。特に平日の日中にデイサービスを利用すれば、家族がその間に仕事や休息をとる時間を確保できますし、ホームヘルパーの力を借りて入浴介助や食事準備を行ってもらえば主介護者の負担が軽減します。介護サービスの利用には市区町村の窓口で要介護認定の申請が必要ですので、地域包括支援センターなどに相談して手続きを進めてください。
地域包括支援センターなどへの相談
若年性認知症と診断された後、または疑われる段階で、活用していただきたいのが公的な相談窓口です。代表的な相談先としては、お住まいの地域包括支援センターがあります。地域包括支援センターは高齢者支援の機関というイメージがありますが、認知症の方や家族全般の相談に応じてくれます。担当の保健師や社会福祉士などが、医療や介護サービスの紹介、福祉制度の手続き案内など包括的にサポートしてくれます。特に若年性認知症の場合、40代や50代ということで福祉制度の情報が行き届きにくい面がありますが、地域包括支援センターに相談すれば各種サービスを紹介・調整してもらえるでしょう。
また、各都道府県および政令指定都市には、若年性認知症支援コーディネーターという専門職が配置されています。若年性認知症支援コーディネーターは、若年性認知症の本人や家族の状況に合わせて総合的なコーディネート支援を行う役割です。具体的には、必要なサービスの情報提供だけでなく、サービス利用の手続き代行や医療機関・就労支援機関への同行支援なども行っています。まさに若年性認知症に特化した心強い相談相手です。支援コーディネーターに連絡したい場合は、各自治体(都道府県や指定都市)の担当窓口や、全国若年性認知症コールセンターに問い合わせると紹介してもらえます。
まとめ
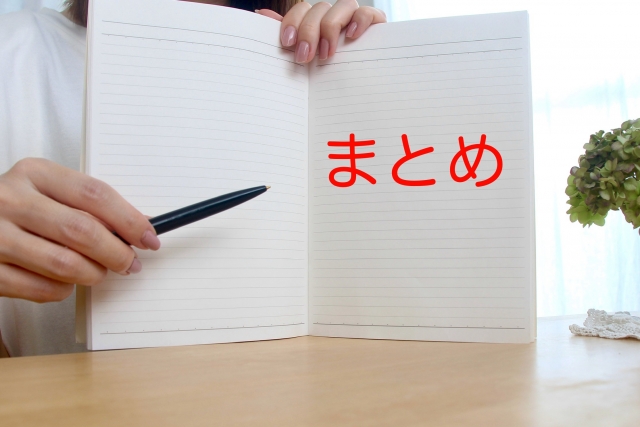
若年性認知症は、本人にも家族にも大きな不安をもたらす病気ですが、早期に気付き適切な対応をとれば、できる限りその方らしい生活を続けることも可能です。ご本人が症状を自覚しにくいからこそ、周囲の理解と支えが欠かせません。少しでも「おかしいな」と感じることがあれば、無理に隠したりせず専門医に相談してください。
診断を受けた後も、利用できる制度やサービスをフル活用しましょう。仕事や社会とのつながりを保ちながら、家族や支援者と協力して生活を続けていく道は必ずあります。国や自治体にも支援の枠組みが用意されていますので、決して一人で抱え込まず、周囲の力を借りながら前向きに歩んでいきましょう。



