認知症は進行に伴い、記憶や判断力の低下だけでなく、日常生活で介助が必要な場面が増えていきます。その支えとなるのが介護保険制度で、訪問介護やデイサービス、グループホーム、特別養護老人ホームなど多様なサービスを利用できます。
ただし、認知症と診断されたすべての方が自動的に給付を受けられるわけではなく、申請や認定の手続きを経る必要があります。この記事では、介護保険の基礎知識や利用できるサービス、自己負担の仕組みや流れを解説します。
認知症と介護保険の基礎知識
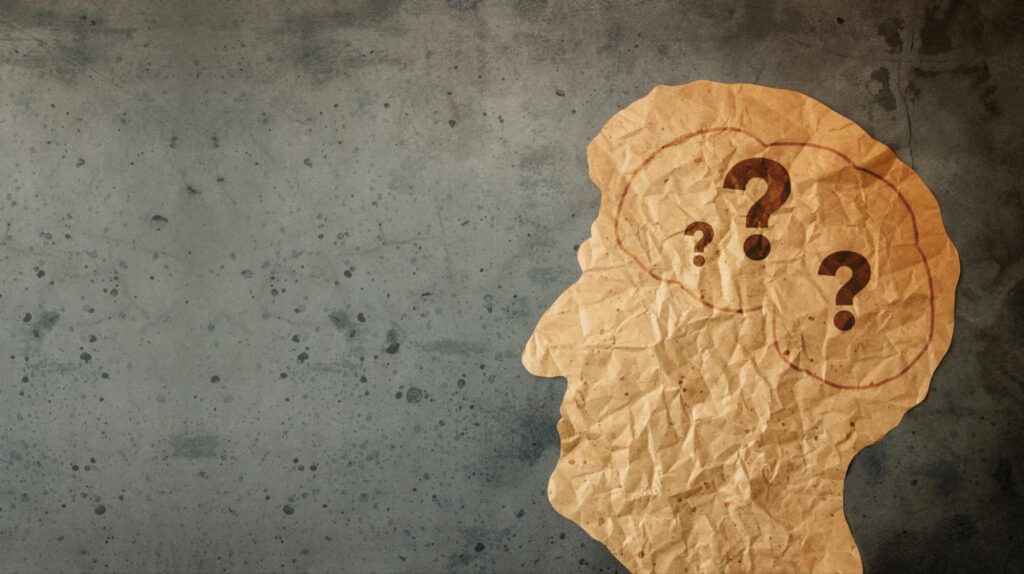
- 認知症とはどのような病気ですか?
- 認知症は、脳の神経細胞が障害を受けることによって、記憶力・思考力・判断力といった認知機能が徐々に低下し、日常生活に支障をきたす病気の総称です。アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など種類があり、症状の現れ方や進行のスピードも異なります。
初期には物忘れが目立つ、同じことを繰り返し尋ねるといった軽い症状から始まり、進行すると時間や場所がわからなくなったり、身近な方の名前を思い出せなくなったりします。さらに進むと、食事や排泄などの日常動作に介助が必要となり、家族だけで支えるのが難しくなることもあります。
- 介護保険の保険料や受けられるサービスを教えてください
- 介護保険は、40歳以上の方が加入する制度です。65歳以上は原則全員が対象となり、40〜64歳の方は特定の病気が原因で介護が必要になった場合に利用できます。
保険料は65歳以上はお住まいの自治体が定める基準額をもとに、所得に応じて段階的に決まります。全国平均では月額6,000円程度ですが、地域や収入によって幅があります。40〜64歳の方は医療保険の保険料とあわせて徴収されます。
利用できるサービスには、訪問介護・訪問看護・デイサービスといった在宅支援、グループホームなどの地域密着型サービス、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所施設があります。認知症の方は状態や暮らしに応じて、これらを組み合わせて利用できます。
参照:『公的介護保険への加入はいつから? 保険料はどのように負担する?』(生命保険文化センター)
- 認知症の方が介護保険の給付対象となるための条件を教えてください
- 認知症と診断された方が介護保険を利用するには、市区町村に申請し、要介護(支援)認定を受ける必要があります。認定は、訪問調査と主治医意見書をもとに審査され、要支援1・2または要介護1〜5のいずれかに判定されます。
要支援に該当する方は生活機能の維持・改善を目的とした軽度の支援が中心で、要介護に該当する方は日常生活に幅広く介助が必要であると認定されます。認定結果によって利用できるサービスの範囲や量が決まるため、このプロセスは大切です。
認知症の方が介護保険で受けられるサービス

- 認知症で要支援や要介護認定を受けるとどのような支援が受けられますか?
- 介護保険では、本人の状態や希望に応じて以下のサービスを受けられます。
・居宅サービス:訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護(デイサービス)、通所リハビリなど
・地域密着型サービス:認知症対応型グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など
・施設サービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など
こうしたサービスを組み合わせることで、自宅生活を続けたい方、医療的ケアを受けながら暮らしたい方、施設での長期生活を希望する方、それぞれに合った支援を受けることができます。
参照:『公表されている介護サービスについて』(厚生労働省)
- 居宅サービスについて教えてください
- 居宅サービスは、できるだけ自宅で生活を続けたい方のための支援です。訪問介護では食事や入浴の介助、掃除や買い物代行などを行います。訪問看護では看護師が体調を確認し、薬の管理や医師との連携による医療ケアも可能です。デイサービスでは入浴や食事、リハビリに加え、ほかの利用者と交流できる場も用意されており、孤独感の軽減にもつながります。
認知症の方は、住み慣れた環境で過ごすことが安心感や症状の安定につながりやすいため、居宅サービスは利用価値の高い選択肢です。
参照:『居宅サービスとは』(長寿科学振興財団)
- 地域密着型サービスについて教えてください
- 地域密着型サービスは、市区町村が提供する小規模の介護サービスです。代表的なのは認知症対応型グループホームで、少人数で共同生活を送りながら介護スタッフの支援を受けます。家庭的な雰囲気で過ごせるため、認知症の方に適した生活環境が整います。
また、小規模多機能型居宅介護では通所・訪問・泊まりを一体的に利用でき、家族の都合や体調変化に合わせて柔軟にサービスを組み合わせることができます。さらに看護小規模多機能型居宅介護では、医療的ケアと生活支援を同時に受けられる点が特徴です。
参照:『地域密着型サービスとは』(長寿科学振興財団)
- 施設サービスとはどのようなサービスですか?
- 施設サービスは、自宅での生活が難しくなった方が長期的に入所して受ける介護です。特別養護老人ホームでは24時間体制の生活介護を受けられ、介護老人保健施設ではリハビリを通じて在宅復帰を目指します。介護医療院は医療ニーズが高い方の生活を支える場で、終末期のケアを含む長期入所が可能です。
認知症が進行し、家族の介護負担が大きくなった場合には施設サービスを選ぶことが現実的な選択肢といえるでしょう。
参照:『施設サービス』(長寿科学振興財団)
介護保険サービスの自己負担額と手続き方法

- 介護保険サービスを利用する場合の自己負担額を教えてください
- 介護保険のサービスには、要介護度ごとに支給限度額が全国共通で定められています。この限度額内であれば、原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担で利用できます。
介護保険サービスの支給限度額
| 区分 | 支給限度額(月額) |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
例えば要介護3の方の場合、月27万円相当までのサービスを利用でき、そのうち自己負担1割なら約2万7,000円、2割負担なら約5万4,000円です。限度額を超えてサービスを使うと全額自己負担です。ただし、高額介護サービス費制度を利用すれば、所得や世帯の条件に応じた上限額を超えた分については払い戻しが行われるため、自己負担を抑えられます。
参照:『サービスにかかる利用料』(厚生労働省)
- 認知症の方が介護保険サービスを受けるための手続きを教えてください
- 利用にはまず市区町村へ申請を行います。その後、専門調査員が自宅で調査を行い、主治医の意見書も併せて審査されます。介護認定審査会で判定されると要介護度が決まり、通知が届きます。認定を受けたらケアマネジャーと契約し、ケアプランを作成して具体的なサービス利用が始まります。
- 介護保険の手続き方法がわからないときはどうすればよいですか?
- 申請や手続きに迷った場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険課に相談するのがおすすめです。職員が申請を代行したり、必要書類の準備を手伝ったりしてくれます。厚生労働省の介護サービス情報公表システムを使えば、地域の事業所やサービス内容を検索でき、比較検討もしやすいです。
参照:『介護事業所・生活関連情報検索』(厚生労働省)
編集部まとめ

認知症と診断された方は、介護保険を通じて自宅支援から地域サービス、施設入所まで幅広い選択肢を持てます。利用には要介護認定が不可欠で、申請・認定・ケアプラン作成を経てサービスが始まります。
自己負担は原則1割(所得により2〜3割)で、限度額を超える分は全額自己負担ですが、高額介護サービス費制度で払い戻しが受けられる仕組みがあります。手続きに迷う場合は、地域包括支援センターや市区町村へ早めに相談するとよいでしょう。



