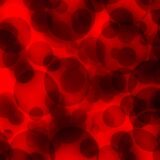認知症は、記憶力や判断力、理解力などが徐々に低下していく病気で、進行すると日常生活にさまざまな支障をきたすようになります。特に、金銭管理や契約手続きといった重要な判断が難しくなってくると、本人の権利や財産を守るために、法律的な支援が必要となることがあります。
そのようなときに活用されるのが成年後見制度です。この制度では、本人の代わりに意思決定や財産管理を担ってくれる後見人が選ばれ、本人が安心して暮らしを続けられるよう支援することができます。後見制度は、認知症の進行度や判断能力に応じて利用できる仕組みが整えられており、家族や支援者にとっても大きな助けになります。
この記事では、認知症と診断された患者さんに後見人が必要となるのはどのような場合か、後見人の種類や制度のしくみ、手続きの流れについて詳しく解説します。あわせて、制度の利用を検討する際の相談先もご紹介します。認知症の患者さんとそのご家族が、より安心して今後の暮らしを考えられるよう、実際の流れに沿って丁寧にお伝えします。
認知症の患者さんで後見人が必要なケースは?

認知症と診断されたからといって、すぐに後見人が必要になるわけではありません。初期の段階では、ご自身で生活や金銭の管理ができる患者さんも多くいらっしゃいます。しかし、病状が進行して判断力が低下してくると、重要な契約や財産の管理において、第三者の支援が必要になる場面が増えてきます。
例えば、不動産の売買や相続の手続き、介護施設への入所契約、銀行口座の管理など、本人の署名や意思確認が必要な場面で、認知機能の低下により適切な判断ができなくなってしまうことがあります。そのままでは法的な手続きが進められなかったり、本人に不利益が生じたりするおそれがあるため、こうした場合に成年後見制度の利用を検討します。
また、認知症の患者さんが高額な買い物をしてしまったり、悪質な訪問販売や詐欺などに巻き込まれたりすることも少なくありません。後見人がついていれば、こうしたトラブルを未然に防いだり、被害を最小限に抑えたりする対応が可能となります。
後見制度は、本人の意思を尊重しながら生活や財産を守るための仕組みです。後見人を選任するには、家庭裁判所を通じた申立てと審査が必要になります。制度の活用には、認知症の進行度や生活の状況を総合的に判断し、早めに準備を進めることが重要です。
後見人とは?成年後見制度の種類と仕組み

認知症の患者さんが安心して暮らしていくためには、本人の意思を尊重しながらも、必要な場面で法的に支えるしくみが求められます。そうした制度のひとつが成年後見制度であり、その中核を担うのが後見人という存在です。
後見人とは、認知症などで判断力が低下した人の代わりに、財産の管理や契約手続きなどを行う法的な支援者です。制度の目的は、本人の権利を守りつつ、生活を安全に維持できるようにすることです。ただし、すべての権限を奪うのではなく、本人の状態や希望に応じて柔軟にサポートの内容が決められます。
成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。利用するタイミングや仕組みが異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに認知症の進行により本人の判断力が低下している場合に利用される制度です。家庭裁判所が本人の状態を調査し、後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任します。どの支援者がつくかは、本人の判断能力の程度によって決まります。
法定後見制度では、後見人には財産管理や契約の同意・代理など、法律行為に関わる広範な権限が与えられます。本人の保護が重視されるため、本人に代わって重要な判断を行うことが可能です。
任意後見制度
任意後見制度は、将来の判断力低下に備えて、本人が元気なうちにあらかじめ自分の支援者(任意後見人)を選んでおく仕組みです。公正証書による契約を結び、実際に判断力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に制度が開始されます。
この制度の利点は、本人の希望や生活スタイルに応じて柔軟に内容を決められる点です。どのような支援を誰に任せるかを自分で決めておけるため、自分らしい暮らしを維持したいと考える方にとっては重要な選択肢となります。
成年後見制度における後見人の種類と役割
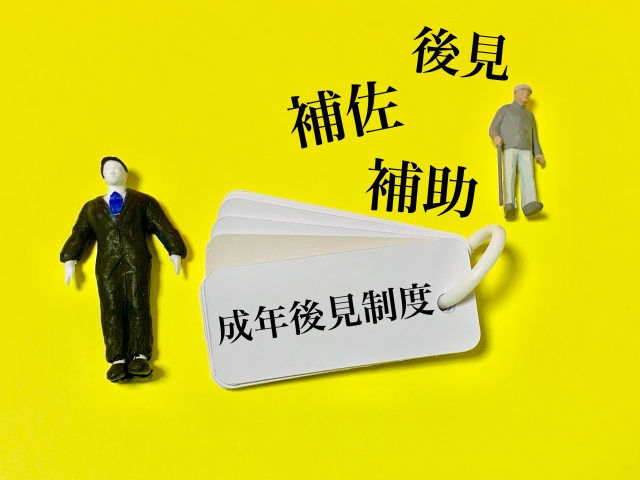
成年後見制度では、認知症などにより判断力が低下した患者さんを法律的に支えるために、本人の状態に応じた3つの支援形態が用意されています。具体的には成年後見人、保佐人、補助人という3つの立場があり、それぞれに担う役割や権限の範囲が異なります。
このように、患者さんの判断能力の程度に合わせて柔軟に支援の内容が設計されていることが、成年後見制度の大きな特徴のひとつです。それぞれの立場について、以下で詳しくご説明します。
成年後見人
成年後見人は、本人の判断力が著しく低下していると認められる場合に選任されます。例えば、認知症が進行して意思表示が困難になった場合などが該当します。成年後見人には、財産管理だけでなく、日常生活に必要な法律行為全般にわたる代理権や取消権が与えられます。
例えば、本人に代わって介護サービスの契約を結んだり、不動産の売却手続きを行ったりすることが可能です。また、本人が不利益になるような契約を結んでしまった場合には、それを取り消すこともできます。本人の生活を支えるうえで、強い権限を持つのがこの成年後見人です。
保佐人
保佐人は、本人にある程度の判断力はあるものの、重要な法律行為については援助が必要とされる場合に選任されます。例えば、預金の引き出しや不動産の契約など、本人だけで行うにはリスクの高い手続きに対して、保佐人の同意や代理が必要になります。
保佐人の役割は、成年後見人ほど広範ではありませんが、本人が不利益を被らないように注意深く支援することにあります。必要に応じて、家庭裁判所に申立てを行い、特定の行為について代理権を追加することも可能です。
補助人
補助人は、日常生活の多くは本人自身で行えるものの、一部の判断においてサポートが必要な場合に選ばれます。補助人が関与できる範囲は限られており、特定の法律行為についてのみ同意や代理が認められます。例えば、携帯電話の契約や高額商品の購入など、本人が誤って不利益を受けるおそれのある場面での支援が中心です。
補助人の支援はあくまで補助的な役割であり、本人の意思を尊重しつつ必要最小限のかたちで関与することが求められます。そのため、本人の自立を保ちながら支えるという観点で設計された仕組みといえます。
【認知症の進行度別】後見制度の手続き方法

認知症と診断された後の後見制度の利用には、家庭裁判所での申立てや書類の準備など、一定の手続きが必要となります。その手続きの内容や進め方は、本人の判断力の状態によって異なります。このセクションでは、認知症の進行度に応じた制度ごとの手続き方法と、申し立ての際に気をつけたいポイントについて解説します。
判断力がある場合|任意後見制度
- 手続き方法
まずは、公証役場で公正証書による任意後見契約を締結します。契約には本人と後見人予定者、そして公証人が立ち会い、内容を文書化します。契約後すぐに後見が始まるわけではなく、実際に判断力が低下したときに、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てることで制度が開始されます。 - 手続きのポイント
任意後見制度は、本人の自由意志で後見人や支援内容を決められる点が大きな特長です。信頼できる人に生活や財産の管理を任せたいと考える方には適した制度です。ただし、公証役場での手続きには費用がかかり、契約書の内容も慎重に確認する必要があります。
判断力が低下している場合|法定後見制度
- 手続き方法
法定後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ては、本人の配偶者や子ども、市町村長などが行うことができ、診断書や財産目録などの必要書類を提出します。その後、家庭裁判所が調査を行い、適切な支援形態と後見人の選任を判断します。 - 手続きのポイント
法定後見制度は、すでに本人の判断が難しくなった状況でも利用できる制度です。ただし、制度の利用開始までには一定の時間を要するため、事前に情報を集めておくことが望ましいです。申立ての際には、専門家の支援を受けることで手続きの負担を軽減し、スムーズに進めることができます。
認知症で後見制度を利用するかどうか悩んだときの相談先

認知症と診断された後、「本当に後見人が必要なのか」「どの制度を選べばよいのか」といった不安や疑問を抱える方は少なくありません。後見制度は法律に基づいた仕組みであるため、正しい情報に基づいて判断することがとても大切です。ここでは、制度の利用を検討するうえで頼れる主な相談先をご紹介します。
家庭裁判所で制度の説明を受ける
成年後見制度を実際に利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要となります。そのため、後見制度について詳しく知りたい場合には、最寄りの家庭裁判所で説明を受けましょう。
家庭裁判所では、窓口や電話で制度の概要や必要書類、手続きの流れなどを丁寧に案内してくれます。申立てにあたっての注意点や、後見人の選任に関する方針なども確認できるため、初めて制度を利用するご家族にとって制度への理解を深めるうえで有用な相談先です。
市区町村の相談窓口で相談をする
多くの市区町村には、地域包括支援センターや高齢者福祉担当の窓口があり、認知症に関する相談を幅広く受け付けています。成年後見制度についても、基本的なしくみや制度の使い方、生活支援との関連などについて案内してもらうことができます。また、地域の社会福祉士やケアマネジャーと連携して、実際の生活状況に応じた支援策を一緒に考えることも可能です。
法テラスなどの法律の専門機関に相談する
成年後見制度は法的な制度であるため、具体的な手続きや内容について専門的な相談をしたい場合には、法テラス(日本司法支援センター)などの法律相談機関を活用しましょう。法テラスでは、制度の概要だけでなく、申立て手続きの流れや書類作成の方法、費用の目安についても詳しく相談することができます。
まとめ

認知症と診断されると、これまで当たり前に行ってきた日常の意思決定や金銭の管理が徐々に難しくなることがあります。そのような状況で患者さんご本人の生活や権利を守る手段として、成年後見制度は重要な役割を果たします。
後見制度には、判断力が残っている段階で自ら後見人を選んで備える任意後見制度と、すでに判断力が低下してから家庭裁判所が支援者を選任する法定後見制度があります。どちらを選ぶかは、認知症の進行度やご本人の希望、ご家族の支援体制によって異なります。
法定後見制度には、本人の判断力に応じて成年後見人、保佐人、補助人の3つの支援形態があり、それぞれに応じた範囲で生活や財産管理をサポートします。特に成年後見人は、広範な代理権限を持ち、重要な契約や財産保護の場面で法的に大きな権限を行使できます。
後見制度を利用するかどうか悩んだときは、家庭裁判所の窓口や市区町村の相談窓口、法テラスなどの専門機関に相談することが大切です。制度の利用には書類準備や申立て手続きが必要となるため、できるだけ早い段階で情報収集を始めることが望まれます。
大切なのは、認知症の患者さんが不利益を受けることなく、安心して自分らしい暮らしを続けていけるような支援体制を整えることです。そのためにも、後見制度の内容や役割を正しく理解し、ご本人とご家族が納得したうえで制度を選びましょう。
成年後見制度は、認知症によって判断力が低下した方の権利と生活を法律の枠組みで支える制度です。ご本人が自分らしく安心して暮らし続けられるよう、状況に応じて適切な支援の選択と制度の活用を検討してください。