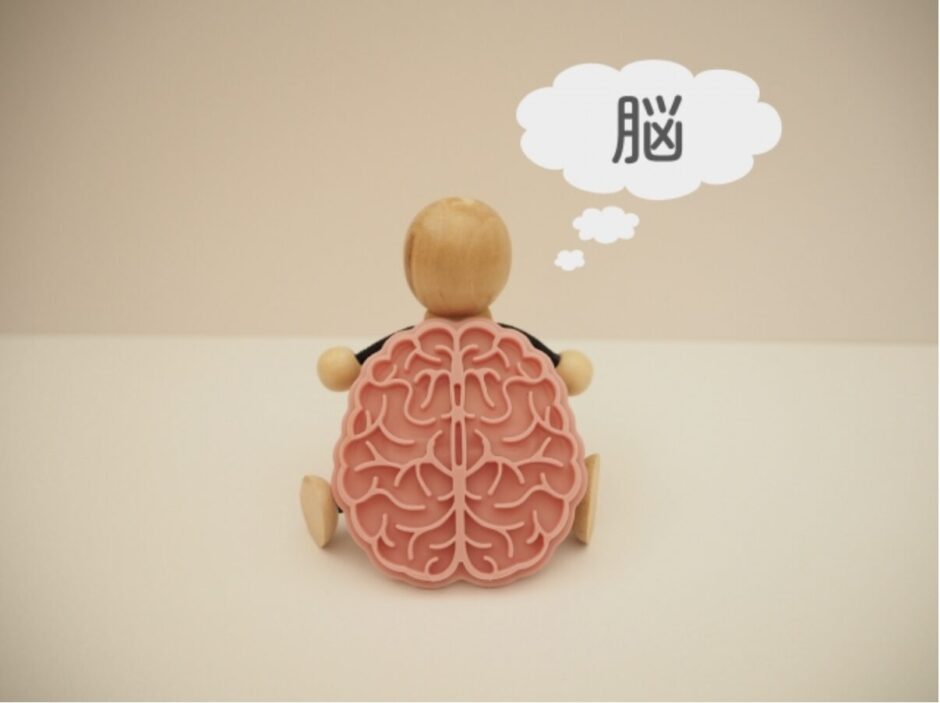私たちの脳は、記憶や思考、感情の調整など、日常生活を支える多くの機能を担っています。しかし、認知症になると、これらの機能が徐々に衰え、思い出す力や判断力、行動のコントロールが難しくなっていきます。一般的な加齢による物忘れとは異なり、認知症では脳の構造や機能が変化します。この変化によって神経細胞の働きが低下し、情報伝達がうまくいかなくなることで進行していきます。
本記事では、認知症の脳にどのような変化が起きるのかを解説します。脳の神経細胞はどのように影響を受け、どのような仕組みで認知機能が低下していくのかを理解することで、認知症の実態に対する理解が深まるでしょう。まずは、認知症の脳の基本的な特徴について見ていきます。
認知症によって脳にどのような変化が起きている?
認知症は、加齢による単なる物忘れとは異なり、脳の構造や機能に明確な変化が生じる病気です。記憶や判断力の低下、行動の変化などの症状は、脳の特定の部位が障害されることで発生します。認知症の種類によって、影響を受ける部位や病理学的変化は異なりますが、共通して神経細胞の損傷や死滅、異常なタンパク質の蓄積が見られます。ここでは、認知症の脳に起こる主な特徴や病理学的な変化について詳しく解説します。
認知症の脳の特徴
認知症の脳では、健康な脳と比べて多くの変化がみられます。特に、脳の一部が萎縮し、記憶や思考に関わる部位の機能が低下することが特徴です。記憶をつかさどる海馬や、判断や感情を調整する前頭葉が萎縮すると、新しい情報を覚えることが難しくなったり、適切な判断を下せなくなったりします。
また、神経細胞の働きが低下すると、脳内の情報伝達が滞り、記憶が曖昧になったり、考えがまとまりにくくなったりします。さらに、脳への血流が低下すると、細胞に必要な酸素や栄養が行き渡らず、脳の働きがさらに衰えてしまいます。
このように、認知症の脳には、神経細胞の衰え、血流の低下、脳の萎縮といった特徴が見られます。これらの変化がどのような仕組みで進行するのかについては、次のセクションで詳しく解説します。
認知症の脳における病理学的変化
認知症が進行すると、脳内では神経細胞の変性や死滅、血流の低下、慢性的な炎症、酸化ストレスなど、複数の病理学的変化が生じます。神経細胞の変性や死滅により情報伝達が障害され、記憶や思考の機能が低下します。一度死滅した神経細胞の再生は難しく、認知機能の低下は不可逆的に進行することが特徴です。
血流の低下も脳機能の衰えに大きく影響します。脳の血流が低下すると、神経細胞に必要な酸素や栄養素が適切に供給されなくなり、エネルギー不足が生じます。この結果、細胞の活動が低下し、新しい記憶を形成する能力や情報処理の速度が低下します。
また、慢性的な炎症も認知症の発症に関わっています。脳内で炎症が続くと、神経細胞がダメージを受け、脳の情報処理能力が低下します。炎症は通常、免疫システムが異物を排除するために起こりますが、認知症の脳では過剰に活性化されることがあり、その結果として神経細胞に悪影響を及ぼすことがあります。
さらに、酸化ストレスは細胞の老化や損傷を進め、神経細胞の機能低下を引き起こします。酸化ストレスとは、体内で発生する活性酸素が細胞にダメージを与える現象であり、これが長期間続くと、神経細胞の働きが低下し認知機能にも影響を及ぼします。
通常の脳と認知症の脳の違い
通常の脳は、神経細胞が互いに連携し、記憶や思考、感情のコントロールなどを円滑に行っています。しかし、認知症の脳では、このバランスが崩れ、情報のやり取りが次第に難しくなります。情報伝達が滞ることで、記憶の保持が困難になり、判断力や注意力も低下していきます。
認知症の脳に見られる変化の一つは、脳の萎縮です。特に、記憶をつかさどる海馬や、意思決定や感情の調整を担う前頭葉が縮小し、これに伴って認知機能の衰えが目立つようになります。また、神経細胞の減少や、それをつなぐシナプスの減少によって、情報のやり取りがスムーズに行われなくなります。これにより、新しいことを覚えにくくなったり、過去の記憶を取り出しにくくなったりします。
加えて、神経伝達物質の減少も脳の働きに影響を与えます。例えば、脳の機能を維持するために重要なアセチルコリンが減少すると、情報の伝達が円滑に行われず、思考や判断のスピードが低下します。また、脳への血流が減少すると、酸素や栄養が十分に供給されず、神経細胞がダメージを受けやすくなり、結果として認知機能が低下します。
認知症の種類別|脳の変化
認知症には複数の種類があり、それぞれ異なる脳の変化を引き起こします。神経細胞が影響を受ける部位によって、症状の現れ方や進行のスピードが異なります。例えば、記憶をつかさどる部分が障害されるタイプでは物忘れが目立ちますが、行動や感情をコントロールする領域に影響が出るタイプでは性格の変化が早期に見られることがあります。
また、認知症の原因も多様であり、脳に異常なタンパク質が蓄積するものや、血流の低下によるもの、外的要因が関与するものなどさまざまです。そのため、認知症の種類によって治療やケアの方法も異なります。
ここでは、代表的な認知症の種類ごとに、脳がどのように変化し、それが症状にどのようにつながるのかを詳しく解説します。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症では、脳にアミロイドβタンパク質が蓄積し、神経細胞の機能を損なうことが知られています。この蓄積が原因で神経細胞の炎症や酸化ストレスが引き起こされ、細胞の働きが低下します。また、タウ蛋白が異常に蓄積することで、神経細胞の構造が崩れ、細胞同士の情報伝達が妨げられます。この影響は特に記憶をつかさどる海馬で顕著に現れ、新しい記憶を形成しにくくなり、過去の出来事を想起するのに時間がかかるようになります。病気が進行すると、大脳皮質の萎縮が広がり、情報処理能力の低下が進むことで、認知機能全体に影響を与える可能性があります。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症では、大脳皮質や脳幹にレビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が蓄積します。このレビー小体は、神経細胞内に形成され、細胞の機能を障害することで脳の働きに大きな影響を与えます。その結果、認知機能の変動が激しくなり、記憶障害が断続的に現れるほか、幻視やパーキンソン病に似た運動障害が生じることが特徴です。レビー小体が蓄積する部位によって、脳の異なる機能が影響を受け、認知機能や運動機能に変化が生じることがあります。脳幹が関与する場合には、自律神経の調整が乱れ、発汗の異常や血圧の変動がみられることもあります。これらの症状は日による変動が多く、病状の進行も不均一である点がほかの認知症と異なる特徴です。
血管性認知
血管性認知症は、脳梗塞や微小な血管の詰まりが原因となることが多く、影響を受ける部位によって症状の現れ方が異なります。脳の血流が低下することにより、神経細胞が十分な酸素や栄養を受け取れなくなり、機能が損なわれることで発症します。また、脳出血により神経細胞が障害されることで生じることもあります。例えば、大脳皮質の一部が損傷を受けると記憶や言語機能に影響が出ることがあり、前頭葉の血流が低下すると計画を立てる力や判断力が低下することがあります。
このタイプの認知症では、神経細胞の働きが損なわれ、認知機能に変化が生じることがあります。影響を受ける領域によって、異なる認知機能が障害されることが特徴です。
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症では、前頭葉や側頭葉の神経細胞が徐々に減少し、残った神経細胞にはタウ蛋白やTDP-43、FUSといった異常な蛋白がたまることが知られています。そのため、前頭葉や側頭葉の萎縮が早い段階から進行し、人格や行動の変化が主な症状として現れます。記憶障害よりも感情や社会的行動の異常が目立つのが特徴で、衝動的な行動や社会的に不適切な発言が増え、対人関係に影響を及ぼすことが多くなります。また、同じ行動を繰り返す常同行動や、特定の物事への強いこだわりが見られることもあります。
病状が進行すると、前頭葉や側頭葉の萎縮が広がり、言語や行動に関わる機能に変化が生じることがあります。前頭側頭型認知症は、行動や感情の変化が中心となる認知症であり、社会生活への影響が特に大きい病気です。
アルコール性認知症
アルコールの長期的な過剰摂取は、脳全体に影響を及ぼし、神経細胞のダメージを引き起こします。特に、大脳皮質の萎縮や神経細胞の変性が進行し、脳の情報処理能力が低下することが知られています。さらに、アルコールは神経伝達物質の働きを乱し、脳の機能を調整するバランスを崩すことで、さまざまな認知機能に影響を与えます。
また、アルコール性認知症にはビタミンB1(チアミン)不足が深く関わっています。ビタミンB1は神経細胞のエネルギー代謝に不可欠ですが、アルコールの過剰摂取により吸収が阻害されるうえ、代謝過程での消費も増加します。これにより、脳の機能が正常に働かなくなり、記憶や認識の低下が生じることがあります。
認知症における脳の変化が及ぼす影響
認知症に伴う脳の変化は、日常生活や認知機能にさまざまな影響を及ぼします。脳の萎縮や神経細胞の変性によって情報の処理速度が遅くなり、記憶や判断力の低下が生じます。特に、記憶をつかさどる海馬が影響を受けると、新しい情報を覚えにくくなったり、過去の出来事を思い出しにくくなったりします。
また、前頭葉の機能が低下すると、感情のコントロールが難しくなり、衝動的な行動や判断の誤りが増えることがあります。これにより、対人関係の変化や社会的行動の障害がみられることもあります。さらに、神経伝達物質の減少や血流の低下が影響し、注意力や集中力の低下が生じ、複数の作業を同時に行うことが難しくなることもあります。
認知症の脳は治療できる?
現在の医学では、認知症の根本的な治療法は確立されていませんが、進行を遅らせたり症状を和らげたりする方法はあります。
アルツハイマー型認知症には、神経伝達物質のバランスを整えるアセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)などが使用され、認知機能低下を遅らせる効果が期待されています。さらに、近年ではアミロイドβを標的とする新たな治療薬として、レカネマブ、ドナネマブが承認されました。この薬は、アルツハイマー病の進行に関与するアミロイドβの蓄積を抑え、病気の進行を遅らせる可能性があります。ただし、すべての患者さんに適用できるわけではなく、早期のアルツハイマー型認知症に対して有効とされています。
血管性認知症では、脳の血流が低下するなどして神経細胞が十分な酸素や栄養を受け取れず、認知機能の低下が生じます。そのため、進行を抑えるには、高血圧や糖尿病、脂質異常症の管理に加え、抗血小板薬(アスピリン、クロピドグレルなど)による脳梗塞の再発予防が有効である可能性があります。また、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけることで、脳の血流を維持し、神経細胞への影響を抑えることができます。
レビー小体型認知症では、根本的な治療法は確立されていませんが、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル)が認知機能の低下を抑え、幻視を軽減する効果があるとされています。ただし、個人差があり、副作用への注意も必要です。
一方、前頭側頭型認知症では、現在のところ有効な薬物治療は確立されておらず、対症療法が中心となります。進行に伴い、行動の変化や感情のコントロールが難しくなるため、症状に応じた環境調整が重要となります。
まとめ
認知症は、脳の萎縮、神経細胞の変性、血流の低下などによって引き起こされる病気であり、その病態は種類ごとに異なります。アルツハイマー型認知症では、アミロイドβやタウタンパク質の異常蓄積が、レビー小体型認知症ではレビー小体の形成が、血管性認知症では脳血流の低下が、それぞれ主要な要因となります。
これらの変化によって、記憶や判断力が低下するだけでなく、感情の不安定さや社会的行動の障害といった症状も現れます。適切な対応を行うことで進行を遅らせ、認知機能を活かしながら生活の質を維持することが重要です。