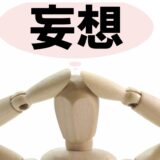「まだら認知症」という言葉を聞いたことがありますか。これは、「1日の中で認知機能の波がある」「できることとできないことの差が大きい」といった認知機能の低下が「まだら」にみられる状態を指します。まだら認知症という言葉自体は、病気の名前ではなく状態を指す言葉で、この状態は認知症の中でも特に、血管性認知症に特有の症状とされています。
本記事では、まだら認知症の特徴や症状、原因、治療方法、そして周囲のサポート方法についてわかりやすく解説します。最後に、「もしかしてまだら認知症かも?」と思ったときに取るべき対策もご紹介します。
【脳の健康度をチェック!】認知機能の維持向上につなげましょう!
まだら認知症の概要と特徴
まだら認知症は、認知機能の低下にばらつきがみられる状態のことで、特に血管性認知症に特徴的な症状とされています。血管性認知症は頻度が高い認知症であり、その理解は予防や早期対応のために重要です。本章ではまだら認知症および血管性認知症の概要と特徴について解説します。
まだら認知症とは
まだら認知症とは、血管性認知症にみられる代表的な症状の一つです。
脳の血管が詰まる、あるいは血管が破れることで脳細胞が損傷されることを脳血管障害といいます。血管性認知症とは、この脳血管障害が原因で生じる認知症のことで、具体的には脳梗塞や脳出血などが含まれます。
血管性認知症は認知症全体の約20%を占めており、アルツハイマー型認知症に次いで2番目に多い認知症です。また、アルツハイマー型認知症との合併も珍しくありません。
まだら認知症の特徴
脳の機能は部位ごとに細かく分かれているため、血管性認知症では脳血管障害が起きた部位によって、低下する能力と保たれる能力に差が生じることが多く、「まだら様」の認知機能低下がみられます。この非均一な認知機能低下が、ほかの認知症と異なる血管性認知症の特徴であり、「まだら認知症」とも呼ばれます。
また、認知機能低下は、アルツハイマー型認知症に多い初期症状の記憶障害(もの忘れ)よりも、注意障害や遂行機能障害が目立つ点が特徴です。なお、早期から歩行障害や嚥下障害、意欲低下、排尿障害がみられる場合もあります。
また、本人が病気を自覚していることが多い点も特徴のひとつです。さらに、脳梗塞などの脳血管障害を起こすたびに、認知症が階段状に悪化するのが典型的です。
まだら認知症の症状
まだら認知症は、血管性認知症に特有の症状の一つとされています。
血管性認知症では、認知機能が均一に低下するのではなく、ばらつきがみられるのが特徴です。また、記憶障害よりも注意障害や遂行機能障害が顕著である点が、ほかの認知症と異なります。さらに、本人が症状を自覚していることが少なくありません。
加えて、歩行障害、嚥下障害、排尿障害、うつ症状などが初期から現れることが多いとされています。
本章では、血管性認知症における具体的な認知機能低下の内容と、認知機能低下以外の症状について詳しく解説します。
注意障害
集中力が続かず、ぼんやりしていたり、ミスが増えたりすることがあります。また、一つの作業を長く続けることが難しくなるため、仕事や家事の効率が低下することがあります。
遂行機能障害
自分で計画を立てたり、物事を順序立てて実行することが困難になります。約束の時間に間に合わない、段取りを考えられないなどの症状が現れることがあります。
意欲低下
活動への関心が薄れ、意欲が低下することがあります。趣味や日常生活への関心が失われ、何をするにも億劫になることが増えます。また、抑うつ症状がみられることもあり、気分が落ち込みやすくなる場合もあります。
運動障害
初期から歩行障害が生じることがあります。動作が緩慢になったり、歩くときのバランスが不安定になり、転倒のリスクが高まるため注意が必要です。また、血管障害による脳の損傷部位によっては、手足の運動麻痺がみられることもあります。
言語障害
発声や発音が不明瞭になり、呂律が回らない、言葉がスムーズに出てこないといった症状が現れることがあります。また、脳血管障害の影響を受ける部位によっては、言葉を適切に話せなくなる運動性失語や、聞いた言葉が理解できない感覚性失語などの症状がみられる場合があります。
嚥下障害
飲み込む動作がスムーズにできず、食事中にむせやすくなることがあります。特に、水やお茶などの液体でむせることが多いとされます。重症化すると、誤嚥性肺炎のリスクが高まるため注意が必要です。
排尿障害
頻尿や尿失禁、排尿困難などの排尿トラブルがみられることがあります。尿意をうまくコントロールできなくなり、トイレの失敗が増えることもあります。
まだら認知症の原因
まだら認知症は、血管性認知症にみられる症状のひとつです。
血管性認知症の原因となる脳血管障害には、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、低酸素脳症、遺伝性血管疾患などが含まれます。
小さな脳血管障害が多数生じた結果、認知症が現れる場合もあれば、脳の部位によっては一度の障害で認知症となる場合もあります。小さな脳梗塞や脳出血は、発症したときに気付かないこともあるため、日々の予防が重要です。
また、脳血管障害の主な危険因子として、高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙、大量飲酒が挙げられます。さらに、不整脈(心房細動)も脳血管障害のリスクとなるため、「脈が飛ぶ」と感じるような症状がある場合や、健康診断で不整脈を指摘されている方は、早めに医療機関へ相談しましょう。
まだら認知症の治療法
まだら認知症の治療は、血管性認知症の治療法と同様に行われます。ただし、一度損傷した脳の細胞は元に戻らないため、現時点では血管性認知症を根本的に治す方法は確立されていません。そのため、治療の中心は脳血管障害の再発予防と、認知症の症状を和らげることとなります。
薬物治療
脳血管障害の再発を防ぐため、高血圧、糖尿病、脂質異常症などを適切に管理することが重要です。そのため、降圧薬や糖尿病治療薬、高コレステロール治療薬が処方されることがあります。
また、脳梗塞後の患者さんには、血液を固まりにくくする薬(抗血小板薬、抗凝固薬)が使われる場合もあります。
飲む薬が増えると、飲み合わせや副作用に注意が必要です。お薬手帳を活用して服用状況を適切に管理し、医師から処方された薬は決められた通りに飲むようにしましょう。
薬の種類が多い場合は、薬の一包化やピルケースの活用を検討すると、飲み忘れ防止に役立ちます。
生活習慣の改善
生活習慣の改善は、脳血管障害の発症予防に重要です。食生活、運動習慣、嗜好品に関して以下に具体的な対策をまとめます。ただし、持病のある方は個別の判断が必要となる場合もあるため、実施する内容についてはかかりつけ医に相談しましょう。
- 食生活:高血圧予防には減塩食(6 g/日未満)が推奨されます。また、代替塩(低ナトリウム塩)を活用するのも有効です。糖質や脂質の過剰摂取を控えることで、糖尿病や脂質異常症の予防にもつながります。
- 運動習慣:適度な運動は肥満を防ぎ、糖尿病、脂質異常症、高血圧のリスクを減らします。さらに、体力の維持や精神の安定にも効果が期待できます。ウォーキングやジョギング、水中歩行は、負担が少ない有酸素運動の例です。ただし、歩行障害がある場合には転倒に十分注意し、リハビリテーション外来などを利用して、専門家の指導を受けながら安全に行うことが大切です。
- 嗜好品:喫煙は脳血管障害だけでなく、心疾患や糖尿病のリスクも高めますので禁煙しましょう。大量飲酒も脳血管障害のリスクを高めるため、飲酒をする場合は節度ある量を心がけることが重要です。必要に応じてアルコール摂取量を見直すことも大切です。
リハビリテーション
適切なリハビリテーションは、身体機能の維持や日常生活の自立度の向上に重要です。
また、まだら認知症がみられる血管性認知症では、認知機能低下に加えて歩行障害や嚥下障害が現れることが多いため、理学療法や作業療法、言語聴覚療法が組み合わせて行われることも少なくありません。デイケアやデイサービス、訪問リハビリテーションなどで専門家の指導を受けることが大切です。
以下に、それぞれのリハビリテーションの一般的な内容を解説します。実際には、日常生活への対策はこれらが協力して行われることもあります。
- 理学療法(PT):立位や歩行練習、下肢や体幹の機能訓練を通じて、歩行の改善や、転倒リスクの軽減を図ります。
- 作業療法(OT):上肢の機能訓練や日常生活に必要な動作の練習を行い、認知機能(記憶力、注意力)の向上をサポートします。さらに、生活自助具の選定や、住環境の調整に関するアドバイスを受けられることもあります。
- 言語聴覚療法(ST):嚥下機能訓練やコミュニケーション訓練を行い、嚥下障害(飲み込みにくさ)や発話の困難さの改善を目指します。
まだら認知症の患者さんへの接し方
まだら認知症では、これまで通りにできることが残されている場合も多く、本人が病気を自覚していることも少なくありません。周囲の方は、本人と相談しながら状況を共有し、困っている部分に応じた適切なサポートを行うことが大切です。
家事や身支度などできることは本人に任せる
できることはできるだけ本人に任せ、自立を尊重しましょう。これまでより時間がかかることがあっても、焦らせず、ゆっくりと見守る姿勢が大切です。できたことが本人の自信につながり、精神の安定や日常生活への満足感を高める効果も期待できます。
ただし、周囲の方は症状の進行や体調の変化がないか、定期的に様子を見守り、必要に応じて柔軟にサポートを行いましょう。
否定、叱責は避ける
頭ごなしに否定したり、失敗を叱責したりすると、本人の自信を失わせる可能性があります。また、精神的な負担が増え、症状の悪化につながることもあるため注意が必要です。言動を尊重しながら、必要に応じてやんわりと受け止めることも大切です。必要に応じて優しく説明し、理解を促すことを心がけましょう。
本人のペースにあわせる
まだら認知症では、できることとできないことの差が大きく、本人自信がもどかしさを感じることもあります。そのため、焦らせず、できる範囲のことは任せながら、無理のないペースで関わることが大切です。
まだら認知症かなと思ったら
認知症に早期に気づき対応することは、適切な医療や介護サービスへつながる重要なステップです。自分自身のほか、家族や友人など周囲の方について「もしかして、まだら認知症かも?」と思う症状に気づいたら、一人で悩まず、医師や専門家に相談しましょう。
専門医を受診する
もの忘れ外来や脳神経内科、精神科、脳外科などが診察を行っています。すでに高血圧や糖尿病などの生活習慣病でかかりつけ医がいる場合は、まずその医師に相談してみるのもよいでしょう。必要に応じて、専門医を紹介してもらえることもあります。
適切な治療を受ける
治療の目的は、症状の悪化を防ぐことや、生活の質を維持することです。
再発予防や症状緩和のためには、薬物療法や運動療法が役立ちます。主治医と相談しながら、自分に合った治療を進めていくことが大切です。
また、持病があり複数の診療科に通院している場合は、治療情報を主治医にきちんと伝えることが大切です。状況を把握してもらうことで、適切な治療が受けやすくなります。
要介護認定など公的支援について調べる
認知症の診断を受けたら、公的支援についても確認しておきましょう。脳血管疾患による認知症の場合、40歳以上であれば65歳未満でも要介護認定を受けられることがあります。
お住まいの市町村にある地域包括支援センターなどの窓口に相談すると、手続きの流れや利用できる支援制度について説明を受けることができます。また、必要に応じて申請に必要な書類の準備や提出手続きのサポートを受けられる場合もあるため、不明点があれば相談してみましょう。
まとめ
まだら認知症は決して珍しい症状ではありません。まだら認知症と血管性認知症について理解することは、本人や家族の不安を軽減し、適切なサポートにつなげるために重要です。また、早期対応によって症状の悪化を防ぐことも期待できます。
もし、自分や身近な方について「まだら認知症かもしれない」と感じたら、一人で悩まずに家族や友人、医療機関に相談しましょう。
参考文献
- 脳血管性認知症 | 健康長寿ネット
- 血管性認知症 | J-STAGE
- 認知症 | 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
- 知っておきたい認知症の基本 | 政府広報オンライン
- 認知症 | 慶應義塾大学 医療・健康情報サイト
- 認知症診療ガイドライン2017 | 日本神経学会
- 認知症に対する非薬物的療法 | 健康長寿ネット
- 介護保険 要介護・要支援認定 | 大阪市
- 高次脳機能障害を理解する | 高次脳機能障害情報・支援センター
- 嚥下障害と誤嚥・咽頭残留の病態及びその対処法 | J-STAGE
- 脳血管障害の排尿障害 | J-STAGE
- 脳卒中ガイドライン2021(改訂2023)| 日本脳卒中学会