認知症は、記憶力や判断力の低下などによって日常生活に支障が生じる病気であり、日本では高齢化の進行とともに深刻な社会的課題となっています。症状が進むと、ご本人の生活の質が損なわれるだけでなく、ご家族や介護者の心身にも大きな負担がかかることがあります。
これまでの認知症治療薬は、症状の進行に応じて対処する治療が中心でした。しかし近年、病気の根本に働きかけることを目指す新しいタイプの治療薬が登場したことで、認知症医療は大きな転換点を迎えています。
特に注目されているのが、アルツハイマー型認知症の原因のひとつとされるアミロイドβというたんぱく質に作用し、病気の進行そのものを遅らせることを目指す薬です。これらの薬は、進行を抑える可能性が期待される一方で、使用できる対象や条件、副作用への注意点など、慎重な判断が求められます。
本記事では、認知症の基本的な特徴をふまえながら、これまでの治療薬と新薬の違いをわかりやすく解説します。さらに、現在日本で使用されている認知症の新薬の種類や費用、治療を始める際の流れなども紹介します。治療の選択肢が広がるなかで、患者さんとご家族が納得して医療と向き合うための一助になれば幸いです。
認知症の基礎知識

認知症とは、脳の細胞が壊れたり機能が低下したりすることで、記憶力や判断力、理解力などの認知機能が衰え、日常生活に支障をきたす病気の総称です。特に高齢者に多く見られ、加齢とともに発症リスクが高まることが知られています。
認知症は単なる物忘れとは異なり、「何年の何月か」「ここがどこか」「目の前の人が誰か」といった状況の理解が難しくなることがあります。そのため、見当違いな行動をとることもあります。こうした変化は日常生活に大きな影響を及ぼし、ご本人の不安や混乱だけでなく、ご家族の戸惑いにもつながります。
また、認知症は多くの場合、ゆっくりと進行する病気です。初期には本人自身も異変を自覚しにくいため、周囲の方が「同じ話を繰り返すようになった」といった小さな変化に気付き、医療機関につなげることが重要です。次の項では、認知症の主な症状と、どのような種類があるのかを詳しく見ていきましょう。
認知症の症状
認知症の症状は、大きく中核症状と行動・心理症状(BPSD)に分けられます。
中核症状とは、脳の働きが直接的に低下することで起こるもので、例えば新しいことが覚えられない、日付や場所がわからなくなる、物事の段取りが組めなくなるといった変化が現れます。こうした症状は認知症の種類や進行度に関わらず多くの方に見られ、日常生活の基本的な行動にも影響を及ぼします。
一方、行動・心理症状(BPSD)は、こうした中核症状や周囲の環境への反応として起こるもので、怒りっぽくなったり、不安や落ち込みが強くなったりするほか、幻覚や妄想、昼夜逆転、徘徊といった行動が見られることもあります。本人のなかでは現実と空想の区別がつかず、不安や恐怖を感じていることも少なくありません。
これらの症状は、生活環境や人との関わり方によっても大きく左右されます。認知症の治療やケアでは、薬だけでなく、安心できる環境づくりや本人の気持ちに寄り添った対応がとても重要です。
認知症の原因
認知症にはいくつかの種類があり、その原因や症状の現れ方には違いがあります。もっとも多いのがアルツハイマー型認知症で、これは脳内にアミロイドβという異常なたんぱく質がたまり、神経細胞が障害を受けることで、記憶を中心とした認知機能が次第に低下していく病気です。
次に多いのが脳血管性認知症で、脳梗塞や脳出血などによって脳の血流が悪くなることで発症します。このタイプでは、症状が階段状に悪化することがあり、身体の麻痺などを伴う場合もあります。
そのほか、レビー小体型認知症は、幻視や手足のこわばり、注意力の波が特徴で、認知症とパーキンソン症状が同時に見られることもあります。また、前頭側頭型認知症は、前頭葉や側頭葉の萎縮によって性格や行動が大きく変化し、常識を逸脱するような行動が見られることもあります。
このように、認知症は一つの病気ではなく、それぞれ異なる背景や経過をもっています。治療や対応も異なるため、早期に適切な診断を受けることが大切です。
これまでの認知症治療薬と新薬の違い

認知症はゆっくりと進行する病気で、長年、進行を完全に止める薬はありませんでした。従来の治療薬は、記憶力の低下や混乱、不安といった症状を一時的にやわらげることが主な目的でした。こうした薬は、脳内の神経伝達物質の働きを整えることで、情報伝達を補い、認知機能を支える役割を果たしてきました。
一方、近年、新たに登場したのが疾患修飾薬(DMT)と呼ばれる薬です。これは、認知症の原因の一つであるアミロイドβに作用し、病気の進行自体を遅らせることを目指しています。長年の研究と臨床試験を経て、ようやく日本でも承認・実用化されました。これにより、認知症治療は対症療法から進行抑制を目指す新しい段階に移行しつつあります。
ただし、こうした新薬には、投与方法、副作用、適応となる病期、必要な検査条件など、注意すべき点が多くあります。すべての患者さんに適用できるわけではなく、専門的な検査や診断を踏まえたうえで、慎重に使用の可否を判断する必要があります。
次に、日本で使用可能な新薬の特徴や費用、治療の流れについて解説します。
日本で処方されている認知症新薬の種類と費用
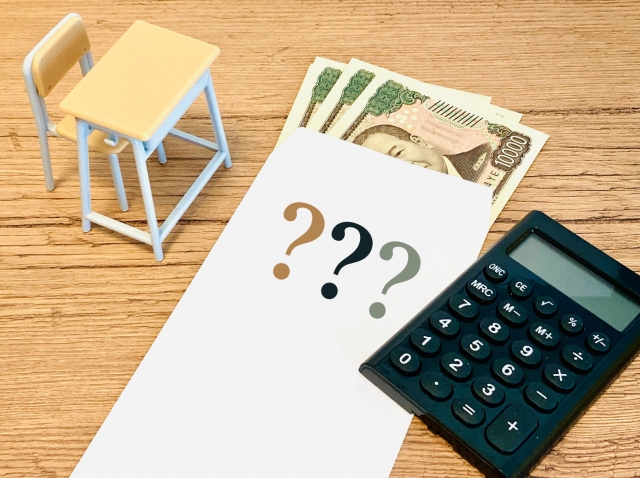
現在、日本で承認されているアルツハイマー型認知症の新薬には、レカネマブ(製品名:レケンビ)とドナネマブ(製品名:ケサンラ)があります。どちらもアミロイドβという異常なたんぱく質を標的とする抗体医薬であり、軽度認知障害(MCI)または軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、かつ脳内にアミロイドβの蓄積が確認された方が対象となります。
レカネマブ
レカネマブは、2023年に日本で最初に承認された抗アミロイドβ抗体薬で、2週間に1回、点滴で投与されます。アミロイドβに結合して脳内から除去することで、アルツハイマー病の進行を数ヶ月から1年程度遅らせる効果が期待されています。
使用にあたっては、PET検査などでアミロイドβの蓄積を確認する必要があります。薬剤費は1年間で約298万円とされていますが、保険適用(3割負担で約87万円/1割負担で約29万円)となっており、高額療養費制度を利用することで実際の負担額はさらに抑えられます。検査費や通院負担もあるため、事前に医療機関での相談が重要です。
ドナネマブ
ドナネマブは、2024年9月に日本で承認された新たな抗アミロイドβ抗体薬で、月1回の点滴投与が基本となります。レカネマブと異なる点として、一定期間の治療(12~18ヶ月)でアミロイドβが十分に除去されたと確認された場合、投与を終了できる可能性があるという特徴があります。これにより、必要以上の長期投与を避けられる点が利点とされています。
薬剤費は年間約308万円と見込まれており、こちらも保険適用により自己負担が軽減されます。通院や検査も継続的に必要なため、専門医療機関での管理が前提となります。
認知症新薬の効果と考えられる副作用

前述のとおり、近年登場した認知症の新薬は、従来薬とは異なり、病気の進行に直接働きかけることを目的としています。一方で、これらの新薬には特有の副作用も報告されており、安全性に配慮した慎重な運用が求められます。この章では、そうした新薬の効果と副作用について詳しく解説します。
認知症新薬に期待できる効果
新薬では、脳内にたまったアミロイドβを減らすことで、病気の進行そのものを遅らせる可能性が示されています。特に、軽度認知障害(MCI)や軽度のアルツハイマー型認知症と診断された段階で使用した場合、数ヶ月から1年程度、認知機能の低下を遅らせる効果が期待されています。一部の患者さんでは、認知機能テストの成績が改善する例も報告されています。
認知症新薬の副作用
新薬には、従来の薬では見られなかった副作用が報告されています。なかでも重要なのが、ARIA(アリア)と呼ばれる脳のむくみや微小出血です。多くは無症状で、定期的なMRI検査で偶然見つかりますが、まれに頭痛や吐き気、意識の混乱といった症状が現れることもあります。
そのほか、点滴による治療のため、注射部位の痛みや倦怠感、軽い発熱などが生じることもあります。副作用の出方は、体調や基礎疾患、体質によっても異なるため、治療中は慎重に経過を観察します。
こうした副作用に備えるため、治療は原則としてMRI検査装置が整っており、副作用に迅速に対応できる体制のある医療機関で行われます。
認知症新薬の適応条件と治療の流れ

新たに登場した認知症の治療薬は、誰にでも使えるわけではありません。安全かつ効果的に使用するためには、医学的な条件を満たし、専門的な検査や医療体制が整った環境で治療を行う必要があります。
ここでは、新薬を使うための適応条件と、実際の治療の進め方についてわかりやすくご紹介します。
認知症新薬の適応条件
新薬はアルツハイマー型認知症と診断されている方のうち、軽度認知障害(MCI)または軽度の認知症に該当する方が対象となります。さらに、アミロイドβが脳内に蓄積していることを検査で確認する必要があります。
アミロイドβの確認には、PET検査や髄液検査など高度な検査手法によって確認されます。これらの検査を行える施設は限られており、診断と治療は認知症診療の経験がある医師のもとで行われることが推奨されています。
また、副作用であるARIA(脳のむくみや出血)を安全に監視するため、1.5テスラ以上のMRI装置が整備された医療機関での治療が必要です。このような要件を満たす医療機関は適正使用管理施設として定められています。
認知症新薬の治療の流れ
治療は、医師からの丁寧な説明と、ご本人・ご家族の同意から始まります。新薬の目的、副作用の可能性、検査や通院の必要性などを理解していただいたうえで、アミロイドβの蓄積を調べる検査を実施します。
検査の結果、薬の使用が適切と判断された場合には、2週間に1回の点滴治療がスタートします。治療は通常、最低でも1年間の継続が見込まれています。治療期間中は、定期的にMRI検査を行い、副作用の有無を確認しながら進めていきます。
新薬治療は、通院や検査が必要なことから、ご本人の体力や通院環境、ご家族の支援体制も大切な要素になります。治療の効果と安全性を両立させるためには、無理のない形で継続できる治療体制の整備が求められます。
今後は、より多くの施設で新薬が安全に使える体制の整備が進むとともに、対象となる患者さんの範囲が広がっていくことも期待されています。
まとめ

これまでの治療薬は、主に症状をやわらげることを目的とした薬が中心でした。しかし、近年登場したレカネマブやドナネマブといった新薬により、病気の根本に働きかけ、進行を遅らせるという新たな治療の可能性が現実のものとなりつつあります。
これらの新薬は、アミロイドβという異常なたんぱく質を脳から除去することで、神経細胞へのダメージを抑えることを目指しています。従来薬と比べて病気の進行を直接的に抑える点が大きな違いであり、特に早期段階での治療によって、認知機能の低下を緩やかにできる可能性があります。
ただし、新薬には点滴による定期的な治療やMRI検査などが必要で、すべての患者さんに適用できるわけではありません。また、治療には副作用への備えや専門的な医療体制も求められます。そのため、治療を始める際には、ご本人やご家族が納得のうえで医師と十分に相談することが欠かせません。
認知症は高齢化に伴い、より多くの方にとって身近な病気となっています。新しい治療法が選択肢として加わった今こそ、早期発見と早期対応の大切さを再確認し、気になる症状がある場合には、専門医に相談することをおすすめします。
参考文献



