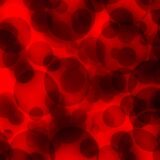認知症の患者さんのなかには、身体はしっかり動かせるものの、日常生活に支障が出ているケースも少なくありません。このような状況でも、介護認定を受けられるのかどうか、不安に思うご家族は多いのではないでしょうか。この記事では、身体が元気でも認知症がある場合に要介護認定が必要な理由や、認定されるための基準、手続きの流れについて詳しくご紹介します。
身体が元気でも認知症での要介護認定が必要な理由

- 身体が元気でも認知症での要介護認定は必要ですか?
- はい、必要です。認知症がある方は身体的な障害がない場合でも、生活のなかで危険な場面が増える、一人での外出が難しくなる、火の始末や金銭管理に不安があるなど、認知機能の低下に伴うリスクが増していきます。本人が危険を察知しにくくなっていたり、間違いに気付かず繰り返したりすることもあるため、日常的な見守りやサポートが必要になります。これらの状態は、介護保険制度上も介護の必要性と評価され、要介護認定の対象となります。
- 要介護認定を受けることで受けられるサービスを教えてください
- 要介護認定を受けると、公的な介護保険サービスが利用できるようになります。具体的には、訪問介護、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリなどの在宅支援に加えて、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)といった施設系サービスも選択可能です。
また、福祉用具の貸与や手すりの設置など、住宅改修も補助の対象となります。認知症対応型のグループホームや小規模多機能型居宅介護など、認知症の患者さんに特化した支援もあります。サービスを利用することで、患者さん自身の安全が確保されるだけでなく、ご家族の介護負担も軽減され、生活の質(QOL)を保ちやすくなります。
- 認知症でも身体は元気な場合に役に立つサービスはありますか?
- はい、多くのサービスがあります。認知症対応型デイサービスは、身体が元気な方でも利用しやすく、他者との交流や生活リズムの維持、軽度の運動、創作活動などを通じて、認知機能の進行を緩やかにする効果が期待されます。
また、訪問介護では、調理や掃除の援助だけでなく、服薬の確認や金銭の管理への見守りといった認知面のサポートに重点を置いた支援が可能です。さらに、GPS付きの見守り端末の貸与や、認知症高齢者徘徊SOSネットワークへの登録など、地域資源を活用した支援も受けられます。これらのサービスは、身体機能が保たれていても自立した在宅生活を続けることが難しい状態にある方にとって、有効な手段となります。
認知症で身体は元気でも要介護判定される基準

- 身体に問題がなくても認知症の要介護認定は受けられますか?
- はい、身体に明らかな障害がなくても、認知症のために日常生活に介助や見守りが必要と判断されれば、要介護認定を受けることが可能です。認知症の初期には、外見上は普通に見えることが多く、ご本人も自立しているつもりで生活されていることがありますが、実際には約束の時間を守れなかったり、買い物でお釣りを間違えたり、服薬管理ができていないといった状況が見られます。これらの状態が生活の安全性を損なうと判断された場合、介護の必要性があると認定される可能性があります。
- 認知症で要介護認定が受けられる基準を教えてください
- 要介護認定では、まず市区町村の職員や調査員による認定調査が行われます。ここでは、記憶力や見当識(時間・場所・人の認識)、判断力、日常生活における意思決定の力などが確認されます。さらに、主治医からの主治医意見書によって、認知症の診断内容や症状の程度が補足されます。
認知症の場合は、認知症高齢者の日常生活自立度という基準が用いられ、生活でどのくらい支援が必要かが判断されます。例えば、道に迷ってしまう、薬の管理ができない、お金の使い方に不安がある、といった場合は、介護が必要と評価されます。身体の動きだけでなく、認知機能の状態も併せて、総合的に要介護度が決定されます。
- 認知症で要介護認定を受けられないのはどのようなケースですか?
- 認知症があっても、症状が軽く、日常生活に大きな支障がない場合は、非該当や要支援と判定されることがあります。例えば、物忘れはあるものの、周囲の声かけやメモなどの工夫で生活できているような場合です。
また、認定調査のときに、本人ができると答えてしまったり、その場では調子がよく見えたりすると、実際の困りごとが伝わらず、軽く評価されてしまうこともあります。そのため、調査の際には、普段の様子をご家族やケアマネジャーが具体的に伝えること、主治医の意見書に実際の生活の様子をしっかり記載してもらうことが大切です。
認知症で要介護認定を受けるための手続き
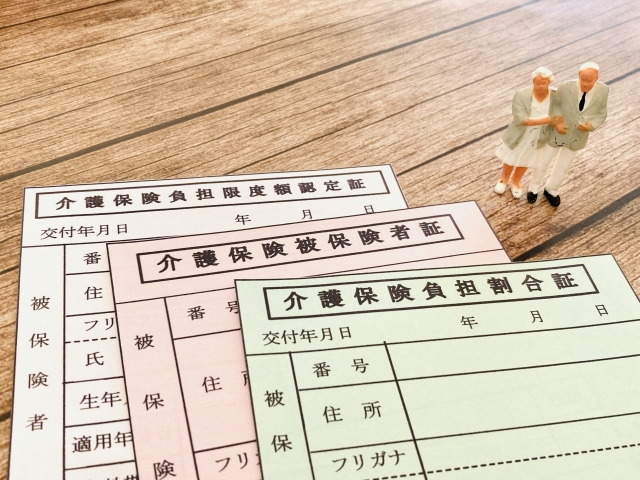
- 認知症で要介護認定を受けるために必要な書類を教えてください
- 申請に必要な主な書類は次の3つです。
1つ目は介護保険被保険者証で、65歳以上の方には交付されています。
2つ目は要介護認定申請書で、本人情報や主治医の連絡先などを記入します。市区町村の窓口やホームページ、地域包括支援センターで入手できます。
3つ目は主治医の情報です。医療機関名や担当医の名前などを記載します。申請はご家族などが代理で行うことも可能で、その場合は委任状が必要になることがあります。
- 認知症で要介護認定を受ける際はどのような手続きが必要ですか?
- 申請は市区町村の窓口か、地域包括支援センターで行います。申請後、調査員が自宅や施設を訪問して、本人の身体や認知機能、生活の様子を確認します。これが認定調査です。
同時に、自治体は主治医に主治医意見書の作成を依頼します。医師は診断内容や症状、生活の状況などを記載します。この調査結果と意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度が決まります。
- 認知症で要介護認定の手続きを行った後の流れを教えてください
- 申請から認定結果の通知までは、おおむね30日以内です。審査会で要支援1・2または要介護1~5のいずれかが判定されます。
認定を受けた後は、ケアマネジャーと相談しながらケアプラン(介護計画)を作成します。この計画に沿って、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスが利用できるようになります。結果に納得できない場合は、不服申立てや再申請も可能です。
- 申請に関して困ったときの相談先はありますか?
- 地域包括支援センターが主な相談窓口です。介護認定の流れや必要書類の準備、申請手続きなどについて丁寧にサポートしてくれます。
そのほか、かかりつけ医、ケアマネジャー、市区町村の高齢者福祉担当課なども相談先になります。認知症の症状をうまく説明できないときや、申請すべきか迷っているときは、早めに相談して進めることが大切です。
編集部まとめ

身体が元気な状態でも、認知症によって日常生活に支援が必要な場合は、要介護認定を受けることができます。介護認定を受けることで、見守りや生活支援など、認知症の症状に合わせたサービスを利用できるようになります。手続きには一定の時間と準備が必要ですが、地域包括支援センターなどの相談機関を活用することでスムーズに進めることができます。早めの申請と適切なサポートの活用が、ご本人とご家族の安心につながります。