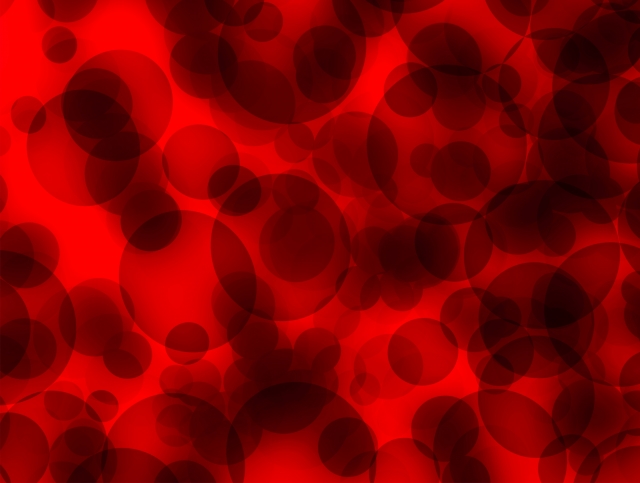「血液検査で認知症がわかるなら受けてみたい」「簡単な検査で早めに知ることができれば安心」そんな風に考えたことはありませんか?採血で簡単に認知症が診断できれば負担が少なく理想的ですが、現在の医療技術でそれは可能なのでしょうか。
この記事では、認知症の診断において血液検査がどのような役割を果たしているのか、また認知症の診断にはどのような検査が必要なのかについて、わかりやすく解説します。最近注目されているMCIスクリーニング検査についても、実態をお伝えします。
認知症は血液検査で診断できる?

認知症の血液検査でわかること
現在の医療では、血液検査だけで認知症かどうかを確定診断することはできません。しかし、血液検査は認知症の診断において重要な役割を果たしています。
臨床現場で主に行われている血液検査の目的は、treatable dementia(治療することで認知機能の改善が期待できる全身性の病気)がないかを調べることです1)。また近年では、代表的な認知症であるアルツハイマー型認知症のスクリーニングとして血液検査を活用する研究も進んでいます。
では、どのような治療可能な病気を血液検査で調べるのでしょうか。
例えば、甲状腺機能低下症やビタミンB12欠乏症などがあげられます。甲状腺の働きが悪くなったり、ビタミンB12が不足したりすると、もの忘れや判断力の低下といった認知症とよく似た症状が現れることがあります。
このような病気は決して珍しいものではありません。実際に、潜在性の甲状腺機能低下症は高齢者の18〜20%に2) 、ビタミンB12欠乏症は60歳以上の方の10〜15%に見られる3)と報告されています。 血液検査では、これらを含むいくつかの原因を調べるために以下のような項目を測定します1)。
- 血算(赤血球数や白血球数)
- 生化学検査(肝機能・腎機能・血糖・電解質など)
- ビタミンB1・B12・葉酸
- 甲状腺ホルモン
- 梅毒などの感染症
これらの検査で異常が見つかった場合、まずその病気の治療を行います。
治療により認知機能が改善すれば、それはtreatable dementiaだったということになります。認知症の診断では最初に血液検査でこうした治療可能な原因がないかを調べることが大切になります。
近年の研究により、アルツハイマー型認知症で脳内に蓄積する特殊なタンパク質(アミロイドβやタウ蛋白)の変化が、血液中にも現れることがわかってきました。
血漿中のアミロイドβ42/40比は、アルツハイマー型認知症の原因と考えられている脳内アミロイド蓄積の有無を反映することが報告されています4)。また、現在注目されているのが、p-tau217(リン酸化タウタンパク質217)という物質の血液検査です。2024年にアメリカで承認されたこの検査は、アルツハイマー型認知症の診断において89%程度の精度を示すとされています5)。さらに、アミロイドβ42/40比とp-tau217を組み合わせることで、診断精度はさらに向上することが報告されています6)。
アミロイドβ42/40比、p-tau217以外にもNfL(ニューロフィラメントL)、GFAP(グリア線維性酸性蛋白)といった血液バイオマーカーが、アルツハイマー型認知症の診断に有用と報告され、臨床への応用が期待されています7)。
血液検査で認知症の診断を確定できる?
血液バイオマーカーの技術は飛躍的に進歩していますが、現時点では認知症の診断を確定することはまだできません。
認知症は日常生活に支障をきたす認知機能の低下という症状に基づいて診断される疾患です。もの忘れがひどくなった、判断力が落ちた、今までできていたことができなくなったといった実際の症状や生活への影響が診断の中心となります。
そのため、どれほど検査技術が進歩しても、検査の数値だけで認知症と診断することはできません。血液検査は認知症の診断をサポートする大切な検査ですが、単独では診断の確定に用いることはできません。ご本人やご家族から聞く日常生活での変化こそが、診断において重要な情報となります。
ただし、今後の技術発展により、認知症診断における血液検査の位置づけは大きくなる可能性があります。
認知症の診断で行われる主な検査

問診、診察
問診と診察が認知症診断の基本となります。医師が患者さん本人およびご家族から詳しく話を伺い、もの忘れの状況や日常生活での変化、症状がいつから始まったか、進行の具合などを確認します。例えば、同じ話を何度も繰り返す、財布のしまい場所を忘れる、といった具体例や、服薬歴・既往歴(過去の病気)、生活習慣なども問診されます。
受診の際には、ご家族からの情報提供が重要です。特にご本人が症状を自覚していない場合や受診時に緊張している場合では、ご家族からの情報によって日頃の様子を共有することができます。
診察においては、もの忘れや認知機能について簡単なチェックを行います。例えば、現在の日時や場所がわかるか、3つの言葉を覚えて数分後に想起できるかなど、簡易的な質問をしながら認知機能低下の有無をみます。同時に神経学的診察を行い、ほかの神経疾患の徴候がないか確認します。
問診・診察の段階で、おおよその症状像や鑑別すべき疾患の見当をつけ、以降の検査計画を立てることになります。
心電図検査
心電図検査も認知症の評価時によく行われる検査の1つです。「認知症の検査なのに、なぜ心電図?」と思われるかもしれませんが、心臓の状態は脳の血流や全身の健康状態に影響するためです。例えば、心房細動という不整脈があると脳梗塞を起こしやすく、それが血管性認知症の原因となる可能性があります。
また、一部の認知症治療薬は心拍に影響を与える場合があるため、治療を安全に行うための心臓チェックも兼ねています。心電図検査は胸や手足に電極をつけて数分で終わる簡便な検査で、心拍のリズムや伝導異常の有無を確認します。
画像検査
画像検査としては脳のCTやMRIがまずあげられます。血管性認知症や正常圧水頭症など認知症のタイプによって画像上の特徴が異なることがあり、診断の手がかりとなります。
さらに、専門的な施設では脳血流を調べるSPECT検査や、脳の代謝やタンパク質の蓄積を調べるPET検査が行われることもあります。近年認可されたアミロイドPET検査では、先ほど取り上げたアミロイドβという物質の脳内蓄積を画像で確認することができます。
神経心理学検査
神経心理学的検査とは、注意・記憶・視覚認知・言語といった脳の機能を客観的に測定するテストです。代表的なものに改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)やミニメンタルステート検査(MMSE)があります。これらのスクリーニング検査に加え、必要に応じてより詳細な神経心理検査を行い、どのような認知機能がどの程度低下しているかを評価します。
また、アルツハイマー型では記憶の低下が目立つ、レビー小体型認知症では注意の変動や幻視がみられる、前頭側頭型認知症では人格変化や言語機能障害が前景に出る、など認知症の型によって現れ方が異なるため、テスト結果は診断の手がかりになります。
神経心理学検査は検査を受ける方にとって負担を感じる場合もありますが、診断の信頼性を高める重要な検査です。検査結果は診断だけでなく今後の治療方針や生活支援計画にも活かされます。
認知症の血液検査『MCIスクリーニング検査』とは

MCIスクリーニング検査の概要
MCIスクリーニング検査は、MCBI社が開発した将来のMCI(軽度認知障害)や認知症のリスクを統計学的に判定する血液検査です。栄養・脂質代謝・炎症免疫・凝固線溶の4群に属する計8種類の血漿タンパク質を質量分析で測定し、独自のアルゴリズムでリスクスコアを算出します。
検査結果はA(低リスク)〜D(高リスク)の4段階で提示されます。検査対象は主に40歳以降の健常者で、すでに認知症と診断されている方は除外されます。 採血量は約2mLと少量で、検体は専門のラボへ送付され、統計処理を経てリスクレポートが作成される仕組みです。
MCIスクリーニング検査でわかることとわからないこと
この検査でわかるのは、アルツハイマー病病態に関与するタンパク質動態から推定されるMCIになりやすさという確率情報です。例えば、D判定はMCIになるリスクが高いという状態を示唆しますが、何年以内に発症するといった時期や確率を個人レベルで特定する力はありません。
注意すべき点として、MCIスクリーニング検査で測定される項目は、国際的に推奨されているアルツハイマー型認知症の血液検査とは異なる指標を用いています。そのため、この検査の妥当性について世界的な大規模研究による客観的な裏付けが十分とはいえません。
さらに、症状のない方への認知症スクリーニング検査については、科学的な根拠が不足しており、専門家の間でも慎重な意見が多いのが現状です。多くの国際専門機関において、症状のない方に対するバイオマーカー・スクリーニングは現時点で推奨されていません7)-9)。日本神経学会などが策定した『認知症に関する脳脊髄液・血液バイオマーカー適正使用指針』では、症状のない方を対象に発症前診断や発症予測を目的として検査を行うことは不適切であると明記されています。
理由としては、症状がない段階で検査で異常が認められても、将来いつ認知症を発症するか、そもそも発症するかどうかを正確に予測することはできないからです。また、検査によってリスクが高いと判明しても、発症を予防するエビデンスのある薬剤は存在しません。このような状況で「将来認知症になる可能性がある」と伝えることは、かえって不必要な不安や心理的負担を与えるおそれがあります。
MCIスクリーニング検査にかかる費用の目安
MCIスクリーニング検査の費用は保険適用外の自費検査となり、医療機関によって多少前後しますがおおよそ2万円前後が目安です。この費用には採血から検査機関での分析、結果報告書の作成までの一連のコストが含まれています。
検査を受ける施設によっては初診料や結果説明の診察料が別途かかる場合もありますので、事前に総額を確認しておくことをおすすめします。
検査の結果が出るまでの時間
検査結果が出るまでにはおおむね2〜3週間程度を要します。採取した血液は専門の検査機関に送られ、複数のタンパク質を高感度の機器で測定し、統計学的解析を行うため、一般的な血液検査よりも時間がかかります。
認知症かもしれないときに相談できる場所
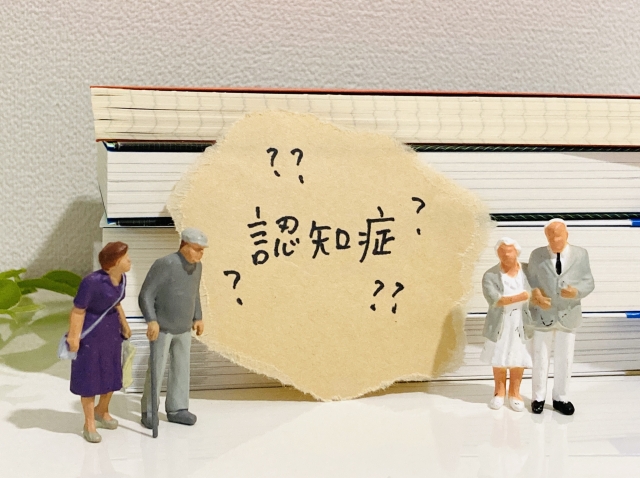
かかりつけ医
もの忘れが気になったとき、まず相談したいのが普段からお世話になっているかかりつけ医の先生です。慣れ親しんだ医師との関係があることで、ご本人もご家族も安心して相談しやすくなります。専門医を受診するうえでもかかりつけ医の情報は貴重であり、その後の診断や治療の流れもスムーズになります。
「もの忘れかもしれない」と気になる症状に気付いた際は、まずかかりつけ医に相談することから始めましょう。日頃の様子をよく知っている先生だからこそ、ちょっとした変化にも気付いてもらいやすいというメリットもあります。
自治体の地域包括支援センター
地域包括支援センターは、ご本人やご家族が抱える「これって認知症?」という不安や、日々の介護の悩みといった相談に乗ってくれる身近な窓口です。「最近、親の様子がおかしい気がするけれど、どこに相談すればいいかわからない」そんなときに頼りになる存在です。
市区町村に設置されており、電話でも来所でも相談でき、費用もかかりません。医療機関への紹介調整はもちろん、介護保険サービスの案内や家族向けの支援プログラムについても詳しく聴くことができます。
医療のことだけでなく、暮らし全般の困りごとについてのサポートを提供しているため、認知症への不安や疑問について気軽に相談できる場所です。特に初期の段階で「どこに相談すればよいかわからない」という場合には、まず地域包括支援センターに連絡してみることをおすすめします。
認知症外来
より詳しい検査や専門的な治療が必要な場合には、認知症外来を受診することになります。認知症外来では詳しい診断を行い、施設によっては高度な画像検査や、研究的な血液バイオマーカー検査などを利用できる場合もあります。かかりつけ医からの紹介が必要な場合が多く、複雑な症状や専門的な鑑別診断が必要なときに受診のタイミングとなります。
専門外来では最新の診断技術や治療法にアクセスできる一方で、初診までに時間がかかることもあります。そのため、まずはかかりつけ医で初期評価を受け、必要に応じて紹介状をもらって受診するという流れが一般的です。一部の医療機関では研究への参加機会もあり、新しい治療法に関する情報を得ることもできます。
まとめ

現在、血液検査だけで認知症かどうかを判断することはできません。ただし、血液検査の技術は進歩しており、将来的には認知症の診断にとってより重要な役割を果たすことが期待されています。
現時点での血液検査は主にビタミン欠乏や甲状腺機能低下など、治療により認知機能の改善が期待できる病気を見つけるために使われています。今後は技術の発展により、認知症のなかでも最も多いアルツハイマー型認知症についても、血液検査によるスクリーニングが普及してくる可能性があります。p-tau217のような新しいバイオマーカーの研究も進んでおり、数年後には血液検査の役割が大きく変わっているかもしれません。
しかし、どのような検査技術が発達しても、認知症で最も重要なのは実際の症状や日常生活への影響です。検査の数値よりも、当事者の困りごとに目を向けることが大切です。もの忘れなどの症状が気になる場合は、まずかかりつけ医に相談してみることをおすすめします。
参考文献
- 1. 認知症疾患診療ガイドライン作成委員会編,日本神経 学会監修:認知症疾患診療ガイドライン 2017,医学 書院,東京,2017
- 2. Gosi SKY, et.al. Subclinical Hypothyroidism. [Updated 2024 Feb 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls
- 3. Baik HW, et.al. Vitamin B12 deficiency in the elderly. Annu Rev Nutr. 1999;19:357-77
- 4. Nakamura A, et.al. High performance plasma amyloid-β biomarkers for Alzheimer’s disease. Nature. 2018 ;554(7691):249-254
- 5. Palmqvist S, et.al. Discriminative Accuracy of Plasma Phospho-tau217 for Alzheimer Disease vs Other Neurodegenerative Disorders. JAMA. 2020;324(8):772-781.
- 6. Rissman RA, et.al. Plasma Aβ42/Aβ40 and phospho-tau217 concentration ratios increase the accuracy of amyloid PET classification in preclinical Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2024;20(2):1214-1224
- 7. Hansson O, et.al The Alzheimer’s Association appropriate use recommendations for blood biomarkers in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2022 ;18(12):2669-2686.
- 8. https://canadiantaskforce.ca/guidelines/published-guidelines/cognitive-impairment/
- 9. 認知症に関する脳脊髄液・血液バイオマーカー, APOE検査の適正使用指針 第2版