認知症は、年齢を重ねることで誰にでも起こりうる病気です。年齢に伴う物忘れとは異なり、記憶や判断力の低下だけでなく、感情や行動にも変化をもたらすため、本人の生活全般や家族の暮らし方にも大きな影響を与えます。長寿化の進展により、認知症は身近な病気としてとらえられるようになってきました。
この記事では、認知症の種類や原因を整理し、前兆期から末期までの症状と接し方、段階に応じた治療、進行を緩やかにする日常の工夫を解説します。
認知症の概要
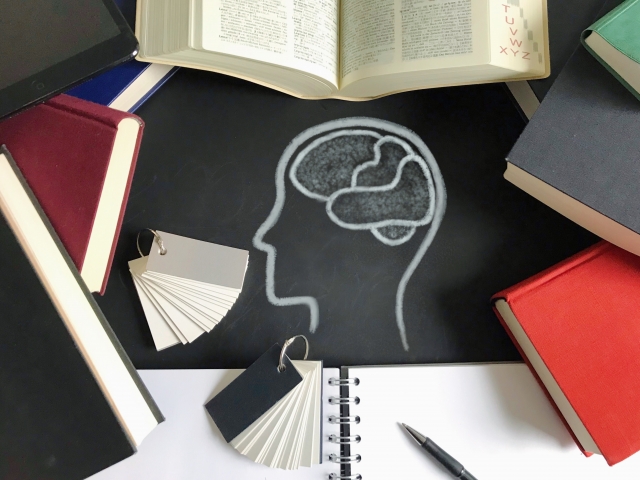
認知症と一口にいっても、原因や症状の現れ方はさまざまです。物忘れが目立つタイプもあれば、行動や気持ちの変化が先に出るタイプもあります。ここでは、代表的な認知症の種類とその原因を解説します。
認知症の種類
認知症にはいくつかの病型があり、進み方や現れやすい症状に特徴があります。
アルツハイマー型認知症は一番多いタイプで、脳にアミロイドβやタウたんぱくといった異常なたんぱく質がたまり、神経細胞の働きが障害されます。初期は新しい出来事を覚えられないといった記憶障害が中心で、徐々に判断力や言葉の理解、生活の段取りなどにも支障が広がります。
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などによる脳血管の障害を背景に発症します。特徴は、発作のたびに段階的に症状が進む点で、記憶障害に加え、手足の麻痺や言語障害といった神経症状を伴うことがあります。
レビー小体型認知症は、レビー小体という異常なたんぱく質が脳に蓄積して起こります。存在しないものが見える幻視や妄想が出やすく、日によって症状の良し悪しに波があるのが特徴です。さらに、身体のふるえや筋肉のこわばりなど、パーキンソン病に似た運動症状を示す場合もあります。
前頭側頭型認知症は、若い世代でも起こることがあり、記憶障害よりも性格や行動の変化が目立ちます。怒りっぽくなる、社会的ルールを守れなくなる、関心が極端に偏るなどの変化が生じ、周囲からは人が変わったようだと受け止められることもあります。
認知症の原因
認知症は脳の神経細胞が障害されることを基盤として起こります。アルツハイマー型ではアミロイドβやタウたんぱくの異常な蓄積、レビー小体型ではレビー小体の形成、脳血管性認知症では血管の障害、前頭側頭型認知症ではタウたんぱくやTDP-43、FUSなどの異常なたんぱく質の沈着による神経細胞へのダメージが原因です。
加齢は大きな要因ですが、それ以外にも糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病、喫煙や運動不足、頭部外傷、アルコールの長期摂取、遺伝的要因なども関与します。これらが複合的に作用し、神経細胞への負担を増やすことで発症や進行につながります。
参照:『認知症疾患診療ガイドライン2017』(日本神経学会)
認知症の段階と症状、接し方

認知症は時間の経過とともに少しずつ進行し、前兆期から初期・中期へと移り変わるごとに症状の表れ方が変化します。各段階の特徴と接し方を理解しておくことが、日常生活を支えるうえで大切です。
前兆期
認知症の初めにあたる段階です。症状は軽く、年齢に伴う物忘れと区別がつきにくいことがあります。本人や家族も少し忘れっぽくなっただけと考えてしまい、受診につながりにくい時期でもあります。
症状
忘れ物や同じ話の繰り返しが増える、慣れた道で迷うといった変化が現れます。会話のなかで言葉が出てこず「それ」「あれ」と表現することが多くなる場合もあります。趣味や交流への関心が薄れ、活動量が減ることもあり、気分の落ち込みやイライラが強まるなど心理的変化が出ることもあります。本人は違和感を自覚するため、不安や焦りを抱えやすく、孤独感を覚えることも少なくありません。
接し方と注意点
「忘れたの?」と指摘するのではなく、「一緒に確認してみよう」と寄り添う声かけが落ち着きにつながります。予定はカレンダーやメモに残し、物の置き場所を決めて習慣化すると混乱を減らせます。不安を訴えたときは否定せず気持ちを受け止める姿勢が安心感をもたらします。
初期
日常生活に少しずつ支障が出始める段階です。本人は失敗を自覚しやすいため、不安や落ち込みが強まり、感情の変化も出現することがあります。
症状
買い物で同じ物を何度も買う、金銭のやり取りで計算が合わない、光熱費や家賃の支払いを忘れるといったトラブルが起こり始めます。料理では手順を飛ばしたり調味料を入れ忘れたりすることが増えます。人や物の名前が出てこず会話が途切れがちになる場合もあります。予定を忘れて約束の時間に遅れる、薬を飲み忘れるなど生活全般に支障が広がることがあります。自分の失敗に気付き、迷惑をかけているのではと悩む方も多く、怒りっぽさや疑い深さが表に出やすいです。
接し方と注意点
できることを続けてもらうことが自尊心の維持につながります。「ありがとう」「助かった」といった感謝の言葉を伝えることで自信を支えることができます。失敗を責めず、必要な部分だけ自然にサポートすることが望ましいです。医師の判断により抗認知症薬やリハビリが始まる段階であり、専門的な支援を取り入れることが進行抑制につながります。
中期
生活全般に支援が必要となり、行動や心理の変化が強まる時期です。介護者の負担も増えるため、周囲の支えが重要です。
症状
時間や場所の感覚があいまいになるため、昼夜逆転が起こりやすいです。外出先から帰れなくなる、同じ質問を繰り返すといった行動が増えます。服薬や食事の自己管理ができず、栄養状態や持病のコントロールに影響することがあります。衣服の着脱が難しくなり、季節に合わない服を重ね着するなどの様子もみられます。徘徊、妄想、幻視といった行動・心理症状が出やすく、不安や興奮が強まる場合もあります。
接し方と注意点
安全な環境を整えることが欠かせません。転倒を防ぐため段差を減らす、火の管理を工夫するなど生活環境を調整します。妄想や幻視は否定せず「心配だったね」と共感を示すと気持ちが落ち着きやすいです。介護の負担は大きいため、デイサービスやショートステイ、訪問介護などを利用し、家族が一人で抱え込まないようにすることが重要です。
末期
日常生活のすべてに介助が必要となり、身体的なケアが中心となる段階です。会話は難しいことが多いですが、表情や仕草といった反応が残ることも多いため、関わり方が生活の質に影響します。
症状
名前を呼んでも反応が乏しくなることが増え、食事・排泄・入浴は全面的な介助が必要です。寝たきりに近づき、誤嚥性肺炎や褥瘡などの合併症が起こりやすい時期です。感染症にかかりやすく、全身状態が急速に悪化することもあります。体重減少や栄養状態の悪化が進み、全身の衰弱が強まります。
接し方と注意点
快適さを重視したケアが必要です。皮膚やお口の清潔を保ち、体位交換や保湿を丁寧に行います。誤嚥を防ぐために食事形態や姿勢を工夫します。意思疎通が難しくても、手を握る、穏やかに声をかけるといった非言語的な関わりが安心につながります。
認知症の進行速度

認知症の進み方は個人差が大きく、病型によっても特徴があります。アルツハイマー型認知症は、ゆっくりと少しずつ悪化することが多く、10年前後をかけて段階的に進みます。脳血管性認知症では、脳梗塞や脳出血といった発作の影響で急に状態が変化し、階段を下りるように悪化するのが特徴です。レビー小体型認知症は症状の波が強く、同じ日でも落ち着いている時間帯と混乱が強い時間帯が入れ替わることがあります。前頭側頭型認知症は行動や性格の変化が早い時期から目立つため、短期間で介助が必要になる場合もあります。
進行の速さには、病型以外の要因も関わることがあります。糖尿病や高血圧などの持病、脳の萎縮の程度、遺伝的な背景のほか、家族や社会的な支えの有無などが影響します。
認知症の治療方法

認知症を完全に治す方法は現時点ではありませんが、進行を遅らせたり症状を和らげたりする治療があります。治療の内容は進行段階によって変わり、薬の選択や目的も異なります。
| 段階 | 主な薬剤 | 適応 |
|---|---|---|
| 前兆期 | レカネマブ ドナネマブ | レカネマブやドナネマブはアルツハイマー型認知症の軽度認知障害(MCI)や軽度の認知症に適応がある。 ドネペジルなどの抗認知症薬はこの段階では適応なし。 |
| 初期 | ドネペジル ガランタミン リバスチグミン レカネマブ ドナネマブ | アルツハイマー型認知症では、コリンエステラーゼ阻害薬3剤(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)が標準治療である。 レカネマブやドナネマブを使用することもある。 レビー小体型認知症ではドネペジルのみ使用できる。 |
| 中期 | ドネペジル ガランタミン リバスチグミン メマンチン | アルツハイマー型認知症では、コリンエステラーゼ阻害薬だけでなくメマンチンも使用可能である。 レカネマブやドナネマブは新規導入できない。 レビー小体型認知症ではドネペジルのみ使用できる。 |
| 末期 | ドネペジル メマンチン | ドネペジルやメマンチンのみが使用できる。 ガランタミンやリバスチグミンは適応外である。 |
アルツハイマー型認知症の前兆期では疾患修飾薬(レカネマブやドナネマブ)を検討します。これらはアミロイドβたんぱくの蓄積を抑え、病気そのものの進行を遅らせることを目的とした新しいタイプの薬です。初期では、記憶障害や注意力の低下に対して、コリンエステラーゼ阻害薬を用います。中期ではメマンチンが加わり、行動や心理の症状(BPSD)にも効果が期待できます。末期では薬の新規導入は少なく、苦痛の緩和や生活の快適さを守る対応が優先されます。一方で、前頭側頭型認知症や脳血管性認知症では、記憶障害など主症状に効果がある薬は存在せず、薬物による進行抑制は難しいのが現状です。そのため、症状に応じた生活支援や介護体制の整備が治療の中心です。
BPSDは、どの段階でも現れることがあります。環境の工夫や介護の方法を調整することが基本ですが、それでも強い不安や幻覚、妄想などが続く場合には、リスペリドンやブレクスピプラゾールなどを少量・短期間で使用することがあります。薬は副作用のリスクがあるため、常に慎重な判断が必要です。
参照:『アルツハイマー型認知症の新しい薬ができました』(東京都福祉局・東京都健康長寿医療センター)
『認知症疾患診療ガイドライン2017』(日本神経学会)
認知症の進行を遅らせるためにできること

認知症の進行を完全に止めることはできませんが、日常生活の工夫によって緩やかにすることは可能です。魚や野菜を中心とした栄養バランスのよい食事は脳の健康を支えます。ウォーキングや軽い体操など無理のない運動を続けることは血流を保ち、神経細胞の働きを支える効果があります。さらに、十分な睡眠を確保し生活のリズムを整えることも、認知機能の維持に役立ちます。
人との交流や趣味活動も重要な要素です。家族や友人との会話を積極的に持ち続けること、地域の集まりやサークルへの参加、音楽や読書などの活動は脳を刺激し、気持ちを安定させる働きがあります。孤立を避け、社会とのつながりを維持するようにしましょう。
また、糖尿病や高血圧といった生活習慣病を治療・管理することは、脳への負担を減らし進行の遅らせることにつながります。薬の内服に加え、定期的な診察で状態を確認することも欠かせません。
まとめ

認知症は病型や段階によって症状や必要な支援が変わります。前兆期に気付けば生活の工夫や治療につなげやすく、初期では自立を支える支援が中心です。中期以降は介護サービスや医療との連携が欠かせず、末期には苦痛を和らげ穏やかに過ごせるようなケアが求められます。
薬による治療はアルツハイマー型やレビー小体型では記憶障害や幻視といった主症状に効果が期待できますが、前頭側頭型や脳血管性では主症状に効く薬がなく、環境調整や生活を支える工夫が中心です。認知症の進行をゆるやかにするために、日々の生活では食事や運動、睡眠のリズムを整え、家族や地域とのつながりを大切にしていきましょう。



